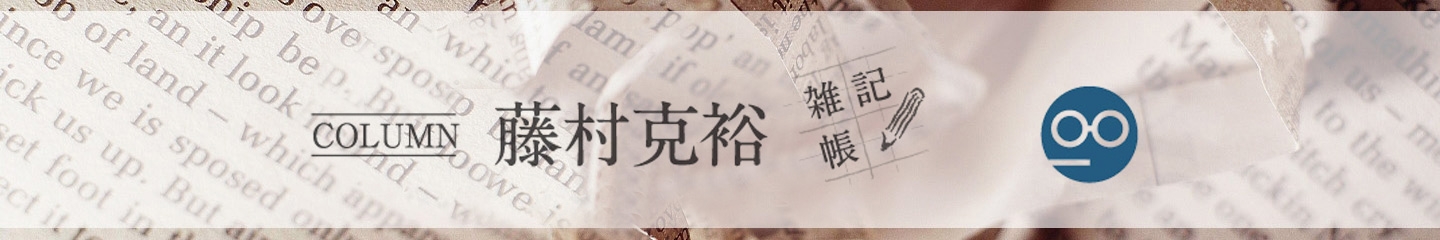

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
ボナール展 その2
2018-12-17
「通りの情景、洗濯女」(1899年)を見てみよう。
まず私の目は、画面右下に広がる赤紫と白と黄色のストライプ面に惹きつけられるが、その上部に女性の頭部を認めると同時に、赤紫と白と黄色の縦縞の広がりはその女性のブラウスで、女性は座っているのではないか、と思わせられる。しかし、女性は膝に白布をかぶせて座っているのではなく、右腕に引っ掛けているのがカゴの持ち手らしいとわかると、そのカゴの中には白い衣類らしきが入っていて、なるほど、この女性がタイトルの「洗濯女」だな、ということになる。女の背中には水色の背もたれらしきがあるが、その左上方には青紫色の不定形があって、それが女性のスカートを描いているらしいとわかった時、水色のところは路面=通りに転じる。タイトルが「通りの情景」となっているわけである。同時に、水色の左の青のマダラは花壇などではなく子供連れの女性の衣服であり、子供は二人、手前に犬。奥に街を行き交う人々。街路樹。馬車に乗っているご婦人もいる。馬車の手前には小さな子供もいる。などなどがわかってくる。つまり、「洗濯女」は座っているのではなく、洗濯物を持って路面を歩いているのだった。絵に描かれた「通りの情景」がこうしたものとして“安定”してくるまで、私たちの目は宙吊りになりながら画面をさまようのである。さまよっている間、形状の前後関係やその意味が反転したり、消えて行ったり出現したりする。描かれた厚紙の固有色=黄土色が随所に小さな不定形として覗いているのが効果的である。厚紙の固有色を利用して、そこに色をあてがうように描画した短時間でのスケッチのような作品。が、こうしてもう十分に出来上がっている。
まず私の目は、画面右下に広がる赤紫と白と黄色のストライプ面に惹きつけられるが、その上部に女性の頭部を認めると同時に、赤紫と白と黄色の縦縞の広がりはその女性のブラウスで、女性は座っているのではないか、と思わせられる。しかし、女性は膝に白布をかぶせて座っているのではなく、右腕に引っ掛けているのがカゴの持ち手らしいとわかると、そのカゴの中には白い衣類らしきが入っていて、なるほど、この女性がタイトルの「洗濯女」だな、ということになる。女の背中には水色の背もたれらしきがあるが、その左上方には青紫色の不定形があって、それが女性のスカートを描いているらしいとわかった時、水色のところは路面=通りに転じる。タイトルが「通りの情景」となっているわけである。同時に、水色の左の青のマダラは花壇などではなく子供連れの女性の衣服であり、子供は二人、手前に犬。奥に街を行き交う人々。街路樹。馬車に乗っているご婦人もいる。馬車の手前には小さな子供もいる。などなどがわかってくる。つまり、「洗濯女」は座っているのではなく、洗濯物を持って路面を歩いているのだった。絵に描かれた「通りの情景」がこうしたものとして“安定”してくるまで、私たちの目は宙吊りになりながら画面をさまようのである。さまよっている間、形状の前後関係やその意味が反転したり、消えて行ったり出現したりする。描かれた厚紙の固有色=黄土色が随所に小さな不定形として覗いているのが効果的である。厚紙の固有色を利用して、そこに色をあてがうように描画した短時間でのスケッチのような作品。が、こうしてもう十分に出来上がっている。
ボナール展 その1
2018-12-17
11月某日、都営地下鉄・大江戸線・六本木駅に降り立ち国立新美術館で開催中の「ボナール展」を目指す人々の流れに加わったつもりでいたのだが、とんだ勘違いであった。多くの人々が、「東山魁夷展」や「日展」の会場に飲み込まれてしまったのである。
「ボナール展」は比較的すいていた。
こうした現実に打ちのめされつつ、作品に目を凝らす。次々に発見があって、ムッチャ面白い。ヘトヘトになった。実は2回目。
何がどう面白いか。その説明はとてもめんどくさい。やってみるが、きっとうまくいかないだろう。
ボナールの絵に描かれた形状は、どの絵も呆れるほどヘンだ。と言うか、フツウじゃない。私は思わず、湯村輝彦氏のイラスト作品を思い出してしまった。
私は昔から湯村氏のイラスト作品が大好きなので、糸井重里氏との共著『情熱のペンギンごはん』はじめ、復刻された絵本『さよならペンギン』など、湯村作品のかなりの量の資料を、いまも書棚に大切に保管している。また、湯村氏の日常を支える買い物先と伝え聞く新宿「伊勢丹」は、私も家人も大好きだが、私どもの場合、「伊勢丹」での買い物は極めて稀にしか実行されない。なぜか? ビンボーだからだ。あ、話が逸れている。ボナールの絵から、思わず湯村氏のイラスト作品を連想してしまったことから、「伊勢丹」やビンボーのことになってしまった。
一見へたくそに見えるが実はとってもうまい人があえてへたくそに見えるように描いている絵がカッコいい、なぜなら、うまいとかヘタとかを超えているからだ、と湯村氏が提唱した有名な概念が「ヘタウマ」である。『さよならペンギン』の湯村氏の絵は、うますぎてため息が出る。このくらい絵のうまい人がやるのが「ヘタウマ」なのだ。湯村氏の「ヘタウマ」作品を観察すれば分かるように、一見ヘロヘロに、はたまた乱暴に描かれているように見えても、着目したディテールへの反応の鋭さとその表現の的確さがある、しかし、そのディテール同士の関係が不合理になっている、これが一つの絵に同居すれば、そこには妙な味わいが生じる。これが「ヘタウマ」の内実である。形状どうしの相互の関係の不合理さは、様々な局面で様々に展開される。正面向きの顔に横向きの横向きの鼻がついていると言うような単純な例から、大小が無視されたり、遠近法が歪んでいたりとか、いちいち例示できない。武器は「線」、そしてキレの良い「色面」だ。色面は多くの場合、ベタ塗りやスクリーントーンやパントーンで与えられるのでカラッとしている 。決して『ナニワ金融道』のように全てを手描きするなどということはしない。「ヘタウマ」をひっさげての湯村氏の登場は、じつにパンチがあった。一世を風靡したのである。
「ボナール展」は比較的すいていた。
こうした現実に打ちのめされつつ、作品に目を凝らす。次々に発見があって、ムッチャ面白い。ヘトヘトになった。実は2回目。
何がどう面白いか。その説明はとてもめんどくさい。やってみるが、きっとうまくいかないだろう。
ボナールの絵に描かれた形状は、どの絵も呆れるほどヘンだ。と言うか、フツウじゃない。私は思わず、湯村輝彦氏のイラスト作品を思い出してしまった。
私は昔から湯村氏のイラスト作品が大好きなので、糸井重里氏との共著『情熱のペンギンごはん』はじめ、復刻された絵本『さよならペンギン』など、湯村作品のかなりの量の資料を、いまも書棚に大切に保管している。また、湯村氏の日常を支える買い物先と伝え聞く新宿「伊勢丹」は、私も家人も大好きだが、私どもの場合、「伊勢丹」での買い物は極めて稀にしか実行されない。なぜか? ビンボーだからだ。あ、話が逸れている。ボナールの絵から、思わず湯村氏のイラスト作品を連想してしまったことから、「伊勢丹」やビンボーのことになってしまった。
一見へたくそに見えるが実はとってもうまい人があえてへたくそに見えるように描いている絵がカッコいい、なぜなら、うまいとかヘタとかを超えているからだ、と湯村氏が提唱した有名な概念が「ヘタウマ」である。『さよならペンギン』の湯村氏の絵は、うますぎてため息が出る。このくらい絵のうまい人がやるのが「ヘタウマ」なのだ。湯村氏の「ヘタウマ」作品を観察すれば分かるように、一見ヘロヘロに、はたまた乱暴に描かれているように見えても、着目したディテールへの反応の鋭さとその表現の的確さがある、しかし、そのディテール同士の関係が不合理になっている、これが一つの絵に同居すれば、そこには妙な味わいが生じる。これが「ヘタウマ」の内実である。形状どうしの相互の関係の不合理さは、様々な局面で様々に展開される。正面向きの顔に横向きの横向きの鼻がついていると言うような単純な例から、大小が無視されたり、遠近法が歪んでいたりとか、いちいち例示できない。武器は「線」、そしてキレの良い「色面」だ。色面は多くの場合、ベタ塗りやスクリーントーンやパントーンで与えられるのでカラッとしている 。決して『ナニワ金融道』のように全てを手描きするなどということはしない。「ヘタウマ」をひっさげての湯村氏の登場は、じつにパンチがあった。一世を風靡したのである。




















