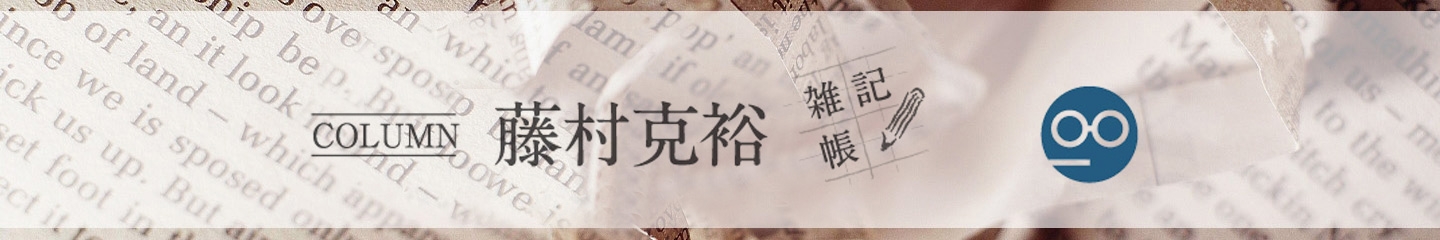

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
写大ギャラリーの森山大道
2021-04-16
明日は雨の予報なので、行きたいところには今日行ってしまおう、と家人と念のために調べてみたら、そこは、あいにく月曜日はお休みだった。なので、地下鉄・丸ノ内線、中野坂上駅から地上に顔を出し、体も出して、山手通りに沿って坂を下り、東京工芸大学芸術学部の「写大ギャラリー」に行った。「森山大道 衝撃的、たわむれ」という展示の見物。
とても面白かった。
新年度を迎えてはいるが、大学もまだコロナで大変だろう。新入生歓迎の催しを兼ねて、美大を始めギャラリーのある大学はどこも展示に趣向を凝らしている(はずだ)。東京工芸大学芸術学部もまた気合の入った企画である。展示構成のご担当は同大教授小林紀晴氏。
森山大道氏について、改めて説明する必要はあるまい。同氏のヴィンテージプリント900点余だったかを所蔵するこの大学の、余裕さえ感じさせる贅沢な展示である。面白くないはずはなく、まんまと(?)実に面白かった。
森山氏が暗室の人であることはすでに知られているが、そのことをまざまざと(?)示す展示である。同じネガから、多様な表情のプリントが生まれてくる暗室作業、その現場感覚のようなものが見事に伝わってくる。しかも、同一のネガから、こんなに違う表情のプリントができるんだよ、というかのようにプリント同士を並べて比較して教育的に見せるのではなく、あえて別のプリントを多数挟んで、物理的に距離をとって展示してあり、挟まった側の「別のプリント」も同じように距離を置いて“反復”して展示しているがゆえに、ある事件性を帯び、“森山世界”に取り込まれ、迷路に迷い込んでしまったような錯覚さえ覚えてくる。このように展示を構成した小林氏の確かな力量(当たり前だが)も同時に重なって見えてくるので、展示された一枚一枚のプリントの見え方はさらに複雑になっている。一度見たくらいではダメだ。だから、会場を二度三度と自然に巡ってしまっている自分に気づかされるのである。後ろを見ては確かめ、横を見ては同じネガフィルムからの変容具合を確かめたりしながら、堪能ということをしてしまった。
とても面白かった。
新年度を迎えてはいるが、大学もまだコロナで大変だろう。新入生歓迎の催しを兼ねて、美大を始めギャラリーのある大学はどこも展示に趣向を凝らしている(はずだ)。東京工芸大学芸術学部もまた気合の入った企画である。展示構成のご担当は同大教授小林紀晴氏。
森山大道氏について、改めて説明する必要はあるまい。同氏のヴィンテージプリント900点余だったかを所蔵するこの大学の、余裕さえ感じさせる贅沢な展示である。面白くないはずはなく、まんまと(?)実に面白かった。
森山氏が暗室の人であることはすでに知られているが、そのことをまざまざと(?)示す展示である。同じネガから、多様な表情のプリントが生まれてくる暗室作業、その現場感覚のようなものが見事に伝わってくる。しかも、同一のネガから、こんなに違う表情のプリントができるんだよ、というかのようにプリント同士を並べて比較して教育的に見せるのではなく、あえて別のプリントを多数挟んで、物理的に距離をとって展示してあり、挟まった側の「別のプリント」も同じように距離を置いて“反復”して展示しているがゆえに、ある事件性を帯び、“森山世界”に取り込まれ、迷路に迷い込んでしまったような錯覚さえ覚えてくる。このように展示を構成した小林氏の確かな力量(当たり前だが)も同時に重なって見えてくるので、展示された一枚一枚のプリントの見え方はさらに複雑になっている。一度見たくらいではダメだ。だから、会場を二度三度と自然に巡ってしまっている自分に気づかされるのである。後ろを見ては確かめ、横を見ては同じネガフィルムからの変容具合を確かめたりしながら、堪能ということをしてしまった。
モンドリアン展に行ってきた
2021-04-13
モンドリアンの絵がたくさん東京に来ている、というのに、見物に行かないという手はないでしょう、というわけで、行ってきたぞ、『モンドリアン展』。
コロナのせいで、予約が必要で、そういうことは、家人がやってくれたのだが、パスワードまで求められて、実に厄介だったようである。パソコン音痴の私は、そうなの? てなもんなのである。
でも、面白かった。何が? だから『モンドリアン展』が。
ともかく初期作品。どれも的確で、すでに非凡さが明らかである。まず、色感がいい。とりわけ明度の低い色。その中にデリケートな調子を見出していく力は並外れている、と見た。
また、コントラストやアクセントで処理したりしない。こういうことが、モンドリアンの力量の確かさを示している。決然とした意志のある筆触で確かな色を置いている。こうした初期作品が多数展示されているのは実に嬉しい。堪能ということをした。
階を降りると、いわゆる「モンドリアン」らしいのが示されている。そのきっかけは「キュビズム」からの影響だというのだが、本当か?
確かに「女性の肖像」(1912年)ではキュビズムとの共通項が見て取れないわけではない。しかし、「コンポジション木々2」では周囲の「枠」の方に目が行ってしまう。信じがたく伸びやかな線の枠である。1916年の「コンポジション」では、滲みで生じている調子の表情に目が行ってしまう。そんなわけで、“ノイズ”の方が私には面白かった。モンドリアンの「キュビズム」受容へは目がいかなかったのである。
モンドリアンがモンドリアン特有の様式を確立し展開していく過程の様子を今回の展示から読み取ろうとしても、それは難しい。『デ・スティル』に横滑りしてしまうのである。とは言え、ふだんあまり目にする事ができないモンドリアンの複数の作品に至近距離から目をこらす事ができる。
私は昔、モンドリアンの絵の黒線から交差する箇所を取り去ると「空間」が貧弱になる、ということについて文を書いた事がある。漫画のコマの枠線が視線の自然な動き(コマを読む順番)を誘導していることとの比較で考えてみたのだったが、その考えは今も変わらない。しかし今回の展示を見て、それ以外にも色々考える事があった。
コロナのせいで、予約が必要で、そういうことは、家人がやってくれたのだが、パスワードまで求められて、実に厄介だったようである。パソコン音痴の私は、そうなの? てなもんなのである。
でも、面白かった。何が? だから『モンドリアン展』が。
ともかく初期作品。どれも的確で、すでに非凡さが明らかである。まず、色感がいい。とりわけ明度の低い色。その中にデリケートな調子を見出していく力は並外れている、と見た。
また、コントラストやアクセントで処理したりしない。こういうことが、モンドリアンの力量の確かさを示している。決然とした意志のある筆触で確かな色を置いている。こうした初期作品が多数展示されているのは実に嬉しい。堪能ということをした。
階を降りると、いわゆる「モンドリアン」らしいのが示されている。そのきっかけは「キュビズム」からの影響だというのだが、本当か?
確かに「女性の肖像」(1912年)ではキュビズムとの共通項が見て取れないわけではない。しかし、「コンポジション木々2」では周囲の「枠」の方に目が行ってしまう。信じがたく伸びやかな線の枠である。1916年の「コンポジション」では、滲みで生じている調子の表情に目が行ってしまう。そんなわけで、“ノイズ”の方が私には面白かった。モンドリアンの「キュビズム」受容へは目がいかなかったのである。
モンドリアンがモンドリアン特有の様式を確立し展開していく過程の様子を今回の展示から読み取ろうとしても、それは難しい。『デ・スティル』に横滑りしてしまうのである。とは言え、ふだんあまり目にする事ができないモンドリアンの複数の作品に至近距離から目をこらす事ができる。
私は昔、モンドリアンの絵の黒線から交差する箇所を取り去ると「空間」が貧弱になる、ということについて文を書いた事がある。漫画のコマの枠線が視線の自然な動き(コマを読む順番)を誘導していることとの比較で考えてみたのだったが、その考えは今も変わらない。しかし今回の展示を見て、それ以外にも色々考える事があった。




















