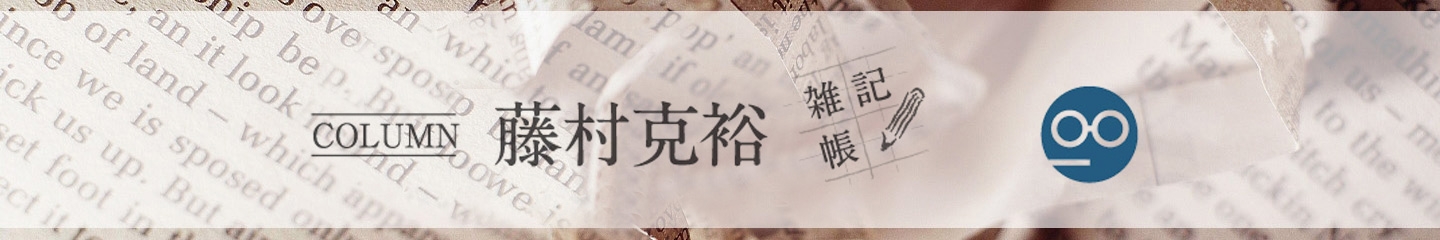

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
「スペース23℃」での榎倉康二展(3)
2025-04-18
西村画廊個展から二ヶ月後に行われた真木画廊個展(5月9日~15日)で「無題」3点が登場した。
壁にピンッ!と直接張った大きな綿布上には、油=廃油を染み込ませた細長い板を綿布に押し当ててできたようなその板の痕跡めいた形状と、その形状からさらに滲み出たしみの形状とがあった。その形状と、その形状をなした細長い板それ自身とを組み合わせていく。あるものはその痕跡上に、あるものはそこからずらして固定し、つまり、今度は、作品の一部として色材=油=廃油と一体化した「版」が登場しただけでなく、「版」が布に作り上げた図像に対して、その「版」によってさらに“出来事”が生じている、ということが強調されたのである。
「版」自体が作品の一部として登場する版画作品の作例を、私はこの他に思い浮かべることができない。これは、榎倉氏独自の発想が展開したもの、と言えるだろう。その結果、「版」からの図像=“痕跡”だけでなく、そこからさらにしみがにじみ出ているという“出来事”、さらに「版」そのものが、その“痕跡”からずれたり、回転している、という出来事も生じていたのである。
それは、同じ年の10月10日~15日のときわ画廊個展で更なる展開を見せた。この時、作品は2点あって、互いに緊密に関係を及ぼし合って、画廊空間全体が作品化していた。「版」である細長い板は、壁に張られた大きな綿布上の図像=“痕跡”から離れて床上に置かれ、まるで実体と影とが反転したような不思議な印象をもたらし、それが2点の作品相互で緊密な関係性を生成させていたのである。私はこの時の榎倉作品に立ち会った時のことを今でもありありと思い出す。ときわ画廊の空間全体が緊張感に満ちていて、あまりにきれいで言葉を失った。こんなにきれいでいいのだろうか、とさえ思いながら立ち尽くしていた。
そのときわ画廊個展の一ヶ月後に「今日の作家’77 絵画の豊かさ」展(11月18日~29日)への出品、翌年(1978年)2月の東京画廊個展、さらに1978年6月からの「べニス・ビエンナーレ」出品、とこの「無題」のシリーズは繋がっていってひと区切りとなった。
その1978年の「ベニス・ビエンナーレ」への出品以降、最初に発表されたのが、今回、「スペース23℃」に展示されている3点を含む西村画廊個展(10月)と「今日の作家〈表現を仕組む〉」展(11月)への出品作「干渉率(空間に)」のシリーズだったのである。
やっと元のところへたどりつけた。回り道が過ぎたかもしれない。
この西村画廊個展と「今日の作家77 絵画の豊かさ」展では、制作時には「版」の役割を果たしていたはずの正方形の物体や他の物体(木っ端のようなもの)は、作品にまったく姿を見せていない。その痕跡だけを残して綿布上から消えたのである。観客は版であり色材でもあったはずの物体、つまり正方形をその一部に備えたなにかしらの物体や木っ端を、画面に残されたその痕跡=図像から想像するしかなくなった。版画では、「版」は、刷りが終われば用済みとなるのが普通なのだから、このシリーズで再び普通の版画の形式に立ち返った、とも言えるだろう。
壁にピンッ!と直接張った大きな綿布上には、油=廃油を染み込ませた細長い板を綿布に押し当ててできたようなその板の痕跡めいた形状と、その形状からさらに滲み出たしみの形状とがあった。その形状と、その形状をなした細長い板それ自身とを組み合わせていく。あるものはその痕跡上に、あるものはそこからずらして固定し、つまり、今度は、作品の一部として色材=油=廃油と一体化した「版」が登場しただけでなく、「版」が布に作り上げた図像に対して、その「版」によってさらに“出来事”が生じている、ということが強調されたのである。
「版」自体が作品の一部として登場する版画作品の作例を、私はこの他に思い浮かべることができない。これは、榎倉氏独自の発想が展開したもの、と言えるだろう。その結果、「版」からの図像=“痕跡”だけでなく、そこからさらにしみがにじみ出ているという“出来事”、さらに「版」そのものが、その“痕跡”からずれたり、回転している、という出来事も生じていたのである。
それは、同じ年の10月10日~15日のときわ画廊個展で更なる展開を見せた。この時、作品は2点あって、互いに緊密に関係を及ぼし合って、画廊空間全体が作品化していた。「版」である細長い板は、壁に張られた大きな綿布上の図像=“痕跡”から離れて床上に置かれ、まるで実体と影とが反転したような不思議な印象をもたらし、それが2点の作品相互で緊密な関係性を生成させていたのである。私はこの時の榎倉作品に立ち会った時のことを今でもありありと思い出す。ときわ画廊の空間全体が緊張感に満ちていて、あまりにきれいで言葉を失った。こんなにきれいでいいのだろうか、とさえ思いながら立ち尽くしていた。
そのときわ画廊個展の一ヶ月後に「今日の作家’77 絵画の豊かさ」展(11月18日~29日)への出品、翌年(1978年)2月の東京画廊個展、さらに1978年6月からの「べニス・ビエンナーレ」出品、とこの「無題」のシリーズは繋がっていってひと区切りとなった。
その1978年の「ベニス・ビエンナーレ」への出品以降、最初に発表されたのが、今回、「スペース23℃」に展示されている3点を含む西村画廊個展(10月)と「今日の作家〈表現を仕組む〉」展(11月)への出品作「干渉率(空間に)」のシリーズだったのである。
やっと元のところへたどりつけた。回り道が過ぎたかもしれない。
この西村画廊個展と「今日の作家77 絵画の豊かさ」展では、制作時には「版」の役割を果たしていたはずの正方形の物体や他の物体(木っ端のようなもの)は、作品にまったく姿を見せていない。その痕跡だけを残して綿布上から消えたのである。観客は版であり色材でもあったはずの物体、つまり正方形をその一部に備えたなにかしらの物体や木っ端を、画面に残されたその痕跡=図像から想像するしかなくなった。版画では、「版」は、刷りが終われば用済みとなるのが普通なのだから、このシリーズで再び普通の版画の形式に立ち返った、とも言えるだろう。
「スペース23℃」での榎倉康二展(2)
2025-04-18
100号や30号の中に配された黒い正方形の形状は、描いたり、写真製版したシルクスクリーンによって刷り上げることで画面に得られたのではないように見える。正方形を有するなにかの物体に色を塗って綿布に押し当てて得られたように感じられる。それは、この「干渉率」のシリーズに取り組む前の「無題」のシリーズを知っているから、そう感じてしまうのかもしれない。とはいえ、正方形の形状を備えたなにかの物体を用いているという印象はぬぐえない。思わず、1972年の写真作品「干渉率B(空間へ)」のシリーズに登場する15×15×15㎝の鉛の立方体を用いたように思い込んでしまいそうだが、あきらかに寸法が違っている。別のなにかが使われているはずである。そのなにかの物体のフロッタージュとか拓本とかという可能性もあるが、シンプルにデカルコマニーと考えるのがいいだろう。もっといえば、凸版によるモノタイプの版画。
その正方形の周囲に広がるにじみ=しみは、黒い色が油性であるゆえに綿布に生じているように見えるが、榎倉氏の手によってにじみ=しみのような表情を得るために“作られて”いるのかもしれず、本当のところが分からない。ここでも私(たち)は、このシリーズの作品以前の榎倉氏の代名詞のような油=廃油=しみの作品の展開をあらかじめ知っているがゆえに判断が危うくなってしまっている。
いずれにしても、今回展示されている「干渉率B(空間へ)」のシリーズでは、画面の中に、黒い正方形の形状をしたものが、唐突に放り出されたような印象を生じている。その理由として、一つには縫い目の水平との関係、二つには綿布の薄さと白さ、その面積の広がり、三つには正方形の傾き。また、会場に一緒に展示されている3点の写真作品がその印象を誘導している感があるのも否めない。
制作されてから長い年月が経ってしまったことが、綿布に散らばる無数の小さなシミからあらわである。この自然のしみが、榎倉氏のしみの作品にあらたな表情を刻々と加えているのだ。
余計なことだが、今回展示されている30号の「干渉率B(空間に‥‥)ーNo.2」は1978年10月23日~11月4日の西村画廊個展「干渉率」においての出品作の一つである。当時の図録に掲載されているからまちがいないだろう。ところが、この文の最初に述べた作品集『榎倉康二 KojiEnokura』の中の「資料編」の年譜の1978年の項には、西村画廊個展「干渉率」開催についての記載がない。理由は分からない。
その正方形の周囲に広がるにじみ=しみは、黒い色が油性であるゆえに綿布に生じているように見えるが、榎倉氏の手によってにじみ=しみのような表情を得るために“作られて”いるのかもしれず、本当のところが分からない。ここでも私(たち)は、このシリーズの作品以前の榎倉氏の代名詞のような油=廃油=しみの作品の展開をあらかじめ知っているがゆえに判断が危うくなってしまっている。
いずれにしても、今回展示されている「干渉率B(空間へ)」のシリーズでは、画面の中に、黒い正方形の形状をしたものが、唐突に放り出されたような印象を生じている。その理由として、一つには縫い目の水平との関係、二つには綿布の薄さと白さ、その面積の広がり、三つには正方形の傾き。また、会場に一緒に展示されている3点の写真作品がその印象を誘導している感があるのも否めない。
制作されてから長い年月が経ってしまったことが、綿布に散らばる無数の小さなシミからあらわである。この自然のしみが、榎倉氏のしみの作品にあらたな表情を刻々と加えているのだ。
余計なことだが、今回展示されている30号の「干渉率B(空間に‥‥)ーNo.2」は1978年10月23日~11月4日の西村画廊個展「干渉率」においての出品作の一つである。当時の図録に掲載されているからまちがいないだろう。ところが、この文の最初に述べた作品集『榎倉康二 KojiEnokura』の中の「資料編」の年譜の1978年の項には、西村画廊個展「干渉率」開催についての記載がない。理由は分からない。
「スペース23℃」での榎倉康二展(1)
2025-04-18
東急大井町線・等々力駅に降り立ち、少し歩いて「スペース23℃」まで行って、「榎倉康二没後30周年展」を見た。
過日、東京画廊+BTAPが、A4・ハードカバー・250ページ近くの大変美しい書物=『榎倉康二 Koji Enokura』を発行した。その発行を記念したシンポジウムがこの展覧会前に「スペース23℃」で非公開で開催されていた。シンポジウムには、当該書物に論考を寄せた熊谷伊佐子氏(美術評論家)、佐原しおり氏(東京国立近代美術館)、光田由里氏(多摩美術大学)、それから、榎倉氏と1960年代初頭の“浪人時代”から濃密な付き合いがあった美術家・藤井博氏とが登場し、東京画廊の佐々木博之氏の司会でそれぞれ貴重な発言をした。その記録映像が展覧会場で流されていたが、会場でこのシンポジウムの映像をすべて視聴するのはきびしい。なぜって、とても長いから。幸い「スペース23℃」のホームページから視聴できる。
榎倉康二氏は、1995年10月、それまでの奥沢の自宅から現在地へと引越すために、その準備作業中に心筋梗塞で亡くなった。52歳だった。あれから30年経ったわけだ。
「スペース23℃」は、榎倉氏夫人の榎倉充代氏が、その引越し先の榎倉氏の仕事場になるはずだった部屋を展示スペースとして2000年に開設した。その後、庭に新たな小ぶりの建物=スペースをつくって、そこに移動し現在に至っている。自然光を取り込んだたいへん美しい空間である。
開設時には、榎倉康二氏の遺作展を四期にわたって開催し、その後も、榎倉氏の作品展や、榎倉氏の父君=画家・榎倉省吾氏の作品展、それから生前の榎倉康二氏と密接な関係があった作家達の個展など、着実な展示活動を継続してきている。じつは私も、榎倉氏と親しかった二人=故八田淳氏の遺作ドローイングや写真作品と資料類による展示、故藤原和通氏の初期作品の写真と資料による展示をさせていただいて、大変お世話になった。「スペース23℃」での榎倉展では、毎回、榎倉氏の作品やドローイング、それから他ではあまり見る機会のない資料も展示されるので、その都度発見や驚きがある。
今回の展示は、1977~78年の「干渉率B(空間に)」のシリーズからの3点と、これらの作品の“原型”と考えてもよさそうな1972年の写真作品「予兆ー鉛の塊・空間へA」のシリーズからの3点による構成である。これに、冒頭で述べたシンポジウムのビデオ映像が加わっている。
シリーズ『干渉率B(空間に)』からの3点は、100号が2点、30号が1点。いずれも、既製の木枠に張られた薄手の綿布(うっすらと木枠のシルエットが透けて見える)に、にじみ=しみをともなった黒い正方形の形状をひとつずつ配した作品である。正方形は、木枠の四辺から離れた任意の位置に、ある傾きを持って配されている(今回は展示されていないが、横長画面中央に正方形が水平・垂直にきっちり配された作品もあるようである)。
木枠に張られた綿布は、どれも、二枚の綿布を縫い合わせて作られており、その縫い目が水平に伸びている。そのことから、縫い目と黒い正方形の位置との関係を強く意識した設定であることが見て取れる。100号や30号の大きさなら一枚の綿布で事足りるのだから、わざわざ二枚の綿布を縫い合わせる必要はない。なのに、わざわざ縫い合わせている。このことからも、榎倉氏はこの作品で、縫い目の水平に特別な役割を担わせていたことは明らかである。
過日、東京画廊+BTAPが、A4・ハードカバー・250ページ近くの大変美しい書物=『榎倉康二 Koji Enokura』を発行した。その発行を記念したシンポジウムがこの展覧会前に「スペース23℃」で非公開で開催されていた。シンポジウムには、当該書物に論考を寄せた熊谷伊佐子氏(美術評論家)、佐原しおり氏(東京国立近代美術館)、光田由里氏(多摩美術大学)、それから、榎倉氏と1960年代初頭の“浪人時代”から濃密な付き合いがあった美術家・藤井博氏とが登場し、東京画廊の佐々木博之氏の司会でそれぞれ貴重な発言をした。その記録映像が展覧会場で流されていたが、会場でこのシンポジウムの映像をすべて視聴するのはきびしい。なぜって、とても長いから。幸い「スペース23℃」のホームページから視聴できる。
榎倉康二氏は、1995年10月、それまでの奥沢の自宅から現在地へと引越すために、その準備作業中に心筋梗塞で亡くなった。52歳だった。あれから30年経ったわけだ。
「スペース23℃」は、榎倉氏夫人の榎倉充代氏が、その引越し先の榎倉氏の仕事場になるはずだった部屋を展示スペースとして2000年に開設した。その後、庭に新たな小ぶりの建物=スペースをつくって、そこに移動し現在に至っている。自然光を取り込んだたいへん美しい空間である。
開設時には、榎倉康二氏の遺作展を四期にわたって開催し、その後も、榎倉氏の作品展や、榎倉氏の父君=画家・榎倉省吾氏の作品展、それから生前の榎倉康二氏と密接な関係があった作家達の個展など、着実な展示活動を継続してきている。じつは私も、榎倉氏と親しかった二人=故八田淳氏の遺作ドローイングや写真作品と資料類による展示、故藤原和通氏の初期作品の写真と資料による展示をさせていただいて、大変お世話になった。「スペース23℃」での榎倉展では、毎回、榎倉氏の作品やドローイング、それから他ではあまり見る機会のない資料も展示されるので、その都度発見や驚きがある。
今回の展示は、1977~78年の「干渉率B(空間に)」のシリーズからの3点と、これらの作品の“原型”と考えてもよさそうな1972年の写真作品「予兆ー鉛の塊・空間へA」のシリーズからの3点による構成である。これに、冒頭で述べたシンポジウムのビデオ映像が加わっている。
シリーズ『干渉率B(空間に)』からの3点は、100号が2点、30号が1点。いずれも、既製の木枠に張られた薄手の綿布(うっすらと木枠のシルエットが透けて見える)に、にじみ=しみをともなった黒い正方形の形状をひとつずつ配した作品である。正方形は、木枠の四辺から離れた任意の位置に、ある傾きを持って配されている(今回は展示されていないが、横長画面中央に正方形が水平・垂直にきっちり配された作品もあるようである)。
木枠に張られた綿布は、どれも、二枚の綿布を縫い合わせて作られており、その縫い目が水平に伸びている。そのことから、縫い目と黒い正方形の位置との関係を強く意識した設定であることが見て取れる。100号や30号の大きさなら一枚の綿布で事足りるのだから、わざわざ二枚の綿布を縫い合わせる必要はない。なのに、わざわざ縫い合わせている。このことからも、榎倉氏はこの作品で、縫い目の水平に特別な役割を担わせていたことは明らかである。




















