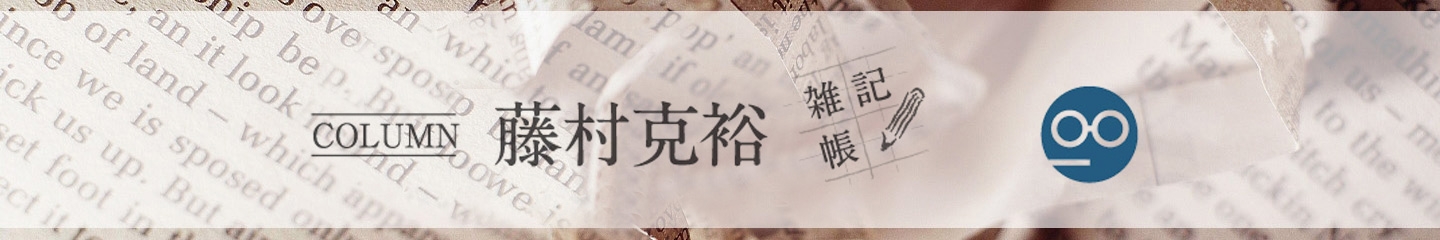

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
「クリスチャン・ボルタンスキー」展を見た。 その2
2019-07-29
会場には作品のキャプションが一切ないので、配布された手元の「マップ」に頼らざるを得ない。暗い中で小さな文字を読むのはとても大変だ。かろうじてこれは「D家のアルバム、1939年から1964年まで」とのタイトルで、1971年の作品、と分かる。所蔵は‥‥、あれま、東京都写真美術館。もっと目を凝らして読んでいくと、ボルタンスキーの友人の家のアルバムの写真をそのまま複写・拡大して年代順に並べて作った作品だ、ということが分かった。ある家族の日常の情報を記憶のように留めた写真群。
ふと、床に設置されている金属枠の同一フォーマットの複数の作品が、壁の写真群と対になっているかのように感じられてくる。
床の作品は、作品と作品との間を歩き回ることができるので、表からも裏からも写真映像で構成された像が見える。裏側には作品を照らすライトがどこにもないのに、ちゃんと見えている。あれっ? なぜ?
注意して観察すると、透明な膜面にシルクスクリーンとかで印刷されているらしい。だからライトなしで見えるのでは? 「マップ」には「グラシン紙に印刷」とある。なるほど、それでフィルムのようなテカリがないのだ。そして、ここに構成されている写真情報もまた、先の“アルバム写真”が引用元ではないか、と確かめようとするが暗くて見えにくく、うまくいかない。再び手元の「マップ」を参照することになった。
「青春時代の記憶」とあって、2001年作。壁の150枚の写真とは出典が無関係で、人々の日常を示す写真群を構成して印刷したものらしい。それが複数、人が通り抜けられる間隔で配されている。当然のことながら、裏側から見ると表側の像の左右が反転している。
別の壁には胸の高さくらいに金属製の箱が設置されている。ちょっと見はジャッドを連想させる。立体を壁にカッコよく設置するには工夫が必要である。横から見てみるが設置の仕掛けがよくわからない。とてもうまい設置である。上から中を覗いてみる。が、よく見えない。薄暗いばかりでなく、上面に目の細かなネットがピンと張られているようなのが分かる。
このあたりで、一つ一つの作品をそのディテールまで凝視するのが大事ではなく、ぼーっと見ることが強いられているのではないか? と気づくことになった。気づいたあとは「見えにくい」というストレスを感じることはなくなった。「記憶」は、確かにぼーっとしているではないか。ぼーっとしていながら、しかし懸命に辿ろうとしたり、思いがけないときに明瞭に蘇る。
ストレスがなくなると、どうしてもボルタンスキーのテクニックへと目が向いていく。
光=電球=スタンドの使い方、コードの使い方、仮設壁どうしの隙間、その使い方、布の使い方、風の使い方、ピントの合った写真とピンボケ写真との使い分け、寸法の判断、ガラス板などの“てかり”の有無の使い分け、色、音、‥‥。
いちいち挙げないが、本当にムッチャ・テクニシャン。上手すぎる。フォーマルでさえある。
こうなってくると、豪速球、というより、うーん、超頭脳派の投球だ、と、ちょっと複雑な気持ちを抱えながら、会場を巡っていくことになったのである。
ボルタンスキー自身の目論見通りインスタレーション作品としてこの展示全体を見ると、ほぼ完璧だと私は思った。先日紹介した友人の意見とは異なってしまったが、しょうがない。もっとも、大阪と東京とでは違う展示になっているはずだ。
一方で、明らかに一つ一つの作品、という単位がある展示である。一つ一つの作品をもっとはっきり見たい、という私の欲望は宙吊りだ。とはいえ、展覧会の会場は明るくなければならない、ということはないのだった。それは理解しているつもりだが。
一緒に訪れていた家人が近づいてきて、スタンドの黒くて丸いシルエットが銃で撃ち抜かれた傷に見えてきて、とても怖い、と言った。なるほど。
最後の出口のある壁には、今度は赤い電球が並んで「ARRIVEE」=到着との文字が形作られていた。ちょっと気恥ずかしくなった。
(2019年7月20日、東京にて)
ふと、床に設置されている金属枠の同一フォーマットの複数の作品が、壁の写真群と対になっているかのように感じられてくる。
床の作品は、作品と作品との間を歩き回ることができるので、表からも裏からも写真映像で構成された像が見える。裏側には作品を照らすライトがどこにもないのに、ちゃんと見えている。あれっ? なぜ?
注意して観察すると、透明な膜面にシルクスクリーンとかで印刷されているらしい。だからライトなしで見えるのでは? 「マップ」には「グラシン紙に印刷」とある。なるほど、それでフィルムのようなテカリがないのだ。そして、ここに構成されている写真情報もまた、先の“アルバム写真”が引用元ではないか、と確かめようとするが暗くて見えにくく、うまくいかない。再び手元の「マップ」を参照することになった。
「青春時代の記憶」とあって、2001年作。壁の150枚の写真とは出典が無関係で、人々の日常を示す写真群を構成して印刷したものらしい。それが複数、人が通り抜けられる間隔で配されている。当然のことながら、裏側から見ると表側の像の左右が反転している。
別の壁には胸の高さくらいに金属製の箱が設置されている。ちょっと見はジャッドを連想させる。立体を壁にカッコよく設置するには工夫が必要である。横から見てみるが設置の仕掛けがよくわからない。とてもうまい設置である。上から中を覗いてみる。が、よく見えない。薄暗いばかりでなく、上面に目の細かなネットがピンと張られているようなのが分かる。
このあたりで、一つ一つの作品をそのディテールまで凝視するのが大事ではなく、ぼーっと見ることが強いられているのではないか? と気づくことになった。気づいたあとは「見えにくい」というストレスを感じることはなくなった。「記憶」は、確かにぼーっとしているではないか。ぼーっとしていながら、しかし懸命に辿ろうとしたり、思いがけないときに明瞭に蘇る。
ストレスがなくなると、どうしてもボルタンスキーのテクニックへと目が向いていく。
光=電球=スタンドの使い方、コードの使い方、仮設壁どうしの隙間、その使い方、布の使い方、風の使い方、ピントの合った写真とピンボケ写真との使い分け、寸法の判断、ガラス板などの“てかり”の有無の使い分け、色、音、‥‥。
いちいち挙げないが、本当にムッチャ・テクニシャン。上手すぎる。フォーマルでさえある。
こうなってくると、豪速球、というより、うーん、超頭脳派の投球だ、と、ちょっと複雑な気持ちを抱えながら、会場を巡っていくことになったのである。
ボルタンスキー自身の目論見通りインスタレーション作品としてこの展示全体を見ると、ほぼ完璧だと私は思った。先日紹介した友人の意見とは異なってしまったが、しょうがない。もっとも、大阪と東京とでは違う展示になっているはずだ。
一方で、明らかに一つ一つの作品、という単位がある展示である。一つ一つの作品をもっとはっきり見たい、という私の欲望は宙吊りだ。とはいえ、展覧会の会場は明るくなければならない、ということはないのだった。それは理解しているつもりだが。
一緒に訪れていた家人が近づいてきて、スタンドの黒くて丸いシルエットが銃で撃ち抜かれた傷に見えてきて、とても怖い、と言った。なるほど。
最後の出口のある壁には、今度は赤い電球が並んで「ARRIVEE」=到着との文字が形作られていた。ちょっと気恥ずかしくなった。
(2019年7月20日、東京にて)
「クリスチャン・ボルタンスキー」展を見た。 その1
2019-07-29
大阪・国立国際美術館で「ボルタンスキー」展を見てきた友人の感想などのことを、以前ここに書いた。だもんで(おっと、ナゴヤ風?)、東京にやって来たら見に行くセキニンがあるような気がした。セキニンだなんて、ただの錯覚なのだが、六本木・国立新美術館に行ってきた。
ボルタンスキーという人の作品のことは1970年代から知っていたような気がする。雑誌などで紹介される彼の作品の情報からは、一見して、ただちにホロコーストとの関係を感じさせられていた。とはいえ、ボルタンスキーのことを詳しく調べてみたことはなかった。今回も図録などを入手していないので、何も知らないに等しい。何年か前に東京都庭園美術館で開催されたボルタンスキー展の記憶もあやふやになってしまっている。その図録も手元にない。ぶっつけ本番で書くのである。
モギリのお姉さんから「会場マップ」を受け取って一歩踏み出すと、なんと、激しい咳き込みの音が繰り返し聞こえてくるではないか。同時に正面壁上方に丸い小さな青いライトが並んで、「DEPART」と文字の形状を示している。ボルタンスキーの世界への「出発」ですよ、と言うのであろう。派手な咳き込みの音が続いている。さらに進むと、右手にスペースが設えられているのが分かる。
案の定、暗いスペースで映像=映画が上映されている。ベンチもある。ありがたい。
映写されていたのは、窓が一つある屋根裏のような部屋で体を壁に預け足を床に投げ出してひどく咳き込み続ける人物の姿である。見れば、人物の頭部は仮面で覆われ、咳き込みながら血のようなものを吐いている。口のところだけ仮面に穴があけられているようだ。ズボンも床も血のようなもので汚れている。咳はずっと続き、血のようなものが繰り返し吐き出される。肺を病んでじきに死んでいく人の姿。イヤーな気がしてくる映像である。カット割りがあったかどうか記憶にない。カメラは上から見下ろすようにして撮影していく。あのように何度も血のようなものをたくさん吐くようにするには、何か仕掛けが必要だろうが、それを詮索するのはいかにも余計なお世話だろう。「咳をする男」。2分28秒の1969年の作品。
引き続き「舐める男」。2分02秒。これも1969年作品。壁を背景に椅子に座らされた人形。女を表している。等身大。この人形の膝のあたりから上方へと仮面を被った男がぺろぺろと舐めていく。無表情の仮面の口から“本物の”舌が出てぺろぺろするのである。カメラはその様子を追っていく。これもまたイヤーな気持ちにさせられる映像だ。
というわけでのっけから、変化球は投げません、豪速球でいきます、とボルタンスキーは言っているのだろう。病、死、貧しさ、愛、欲望、‥‥、そういう厄介な問題群を、豪速球で、ど真ん中目指して。
おののきながら次の部屋に踏み込む。暗い。展示されているものがはっきりとは見えない。
私の老眼は、夕方になると物差しの目盛が見えにくくなった、と気づいた時から始まった。つまり、暗いということは、見えにくい状態があえて作り出されている、ということだ。それは老人に対してばかりではないだろう。
というか、窓のない展示空間は本来どこからも光が届かず真っ暗だから、電気の力で明るさが作り出される。どんな明るさも暗さも人為的、と言ってよい。光源は作品と一体になった黒い塗装の“スタンド”(正式な名称が分らない)や複数の裸電球である。シーリングライトは使われていなかったようだが、確認を怠った。加えて壁が全てグレイに塗られて(グレイの紙が貼られて)いる。
そのグレイ塗装(あるいは壁紙)の壁には、日常のスナップ写真(モノクロ)らしきを一定の大きさに引き伸ばして、整然と縦に10枚横に15列、計150枚、格子状に展示してある。すごい物量である。それは了解できる。が、暗くて写真の“中身”がよく見えない。ある雰囲気が伝われば十分、というのだろうか?
つづき→
ボルタンスキーという人の作品のことは1970年代から知っていたような気がする。雑誌などで紹介される彼の作品の情報からは、一見して、ただちにホロコーストとの関係を感じさせられていた。とはいえ、ボルタンスキーのことを詳しく調べてみたことはなかった。今回も図録などを入手していないので、何も知らないに等しい。何年か前に東京都庭園美術館で開催されたボルタンスキー展の記憶もあやふやになってしまっている。その図録も手元にない。ぶっつけ本番で書くのである。
モギリのお姉さんから「会場マップ」を受け取って一歩踏み出すと、なんと、激しい咳き込みの音が繰り返し聞こえてくるではないか。同時に正面壁上方に丸い小さな青いライトが並んで、「DEPART」と文字の形状を示している。ボルタンスキーの世界への「出発」ですよ、と言うのであろう。派手な咳き込みの音が続いている。さらに進むと、右手にスペースが設えられているのが分かる。
案の定、暗いスペースで映像=映画が上映されている。ベンチもある。ありがたい。
映写されていたのは、窓が一つある屋根裏のような部屋で体を壁に預け足を床に投げ出してひどく咳き込み続ける人物の姿である。見れば、人物の頭部は仮面で覆われ、咳き込みながら血のようなものを吐いている。口のところだけ仮面に穴があけられているようだ。ズボンも床も血のようなもので汚れている。咳はずっと続き、血のようなものが繰り返し吐き出される。肺を病んでじきに死んでいく人の姿。イヤーな気がしてくる映像である。カット割りがあったかどうか記憶にない。カメラは上から見下ろすようにして撮影していく。あのように何度も血のようなものをたくさん吐くようにするには、何か仕掛けが必要だろうが、それを詮索するのはいかにも余計なお世話だろう。「咳をする男」。2分28秒の1969年の作品。
引き続き「舐める男」。2分02秒。これも1969年作品。壁を背景に椅子に座らされた人形。女を表している。等身大。この人形の膝のあたりから上方へと仮面を被った男がぺろぺろと舐めていく。無表情の仮面の口から“本物の”舌が出てぺろぺろするのである。カメラはその様子を追っていく。これもまたイヤーな気持ちにさせられる映像だ。
というわけでのっけから、変化球は投げません、豪速球でいきます、とボルタンスキーは言っているのだろう。病、死、貧しさ、愛、欲望、‥‥、そういう厄介な問題群を、豪速球で、ど真ん中目指して。
おののきながら次の部屋に踏み込む。暗い。展示されているものがはっきりとは見えない。
私の老眼は、夕方になると物差しの目盛が見えにくくなった、と気づいた時から始まった。つまり、暗いということは、見えにくい状態があえて作り出されている、ということだ。それは老人に対してばかりではないだろう。
というか、窓のない展示空間は本来どこからも光が届かず真っ暗だから、電気の力で明るさが作り出される。どんな明るさも暗さも人為的、と言ってよい。光源は作品と一体になった黒い塗装の“スタンド”(正式な名称が分らない)や複数の裸電球である。シーリングライトは使われていなかったようだが、確認を怠った。加えて壁が全てグレイに塗られて(グレイの紙が貼られて)いる。
そのグレイ塗装(あるいは壁紙)の壁には、日常のスナップ写真(モノクロ)らしきを一定の大きさに引き伸ばして、整然と縦に10枚横に15列、計150枚、格子状に展示してある。すごい物量である。それは了解できる。が、暗くて写真の“中身”がよく見えない。ある雰囲気が伝われば十分、というのだろうか?
つづき→
土砂降りの国分寺駅に降り立った日のこと その2
2019-07-19
「清水多嘉示」のお嬢さん=青山さんは、展示されていた写真資料を示しながら、清水多嘉示がどのようにパリで「首」の作品群を作っていたかを教えてくださった。学生が順番にモデルを務めてそれを勉強したらしい。そうして作った作品は石膏に置き換えられ、保管され、やがて日本に持ち帰られたのである。で、思わず尋ねてしまった。ご実家は相当に裕福だったのでしょうか?
かなり不躾で失礼な質問だった。
が、青山さんは、清水多嘉示の実家は長野県でも大きな地主でとくに養蚕で有名な家柄だった、ということを丁寧に教えてくださった。パリへの送金は幾度も行われ、中には当時のお金で80円ほどをパリに送金した記録が残っている、ということさえ教えてくださった。そんなことを伺いながら、私と家人は会場の順路を逆に巡ってしまっていたことに気づくことになった。
清水多嘉示は油絵を学ぶためにパリに行ったのだが、ブールデルの作品と出会って彫刻を始めることになったのだそうだ。だから、パリには油絵用と彫刻用と二つのアトリエがあったそうだ。不覚にも知らなかった。
小ぶりの全身像の前まで連れて行ってくれた青山さんは、これは、初めて作った全身像で、ブールデルから、これはとてもいい作品だからブロンズにしておきなさい、と言われた作品です、と教えてくれたり、戦時中に作られた母子像の前で、こんなギリシャ風の衣服ではなくもんぺ姿にしろ、と言われても決して応じなかった、と聞いています、と教えてくださったり、赤ちゃんが眠っている像の前で、このモデルは私です、と教えてくださったり、素晴らしい首の作品の前で、この作品のモデルはムサビの学生さんだった人で残念ながらもう亡くなられました、と教えてくださったりした。戦後作られた三人の女性が輪になったあの有名なモニュメント作品の原型の前でも、様々なエピソードを教えてくださった。
そんなわけで、お嬢様の解説付きでもう一度、順路通りに鑑賞できたのだった。とても贅沢な時間だった。
それだけではない。青山さんは、出口から一旦出たところの扉の部屋に案内してくださったのである。
そこには、デッサンや油絵、各種資料が部屋中びっしりと、床のたくさんのテーブル上にも、もちろん壁にも梁にも、全く隙間なく、展示されていた。どれも実に興味深く、丁寧に見たり読んだりするには、時間が足りない。会期末に訪れたことを後悔していた。
とりわけ、終戦後すぐの8月16日の日付で、「特攻寺」なるものを提案するためのデッサンが描かれ、文章も書かれていたことに驚いた。こうしたことの意味を考えるにはじっくり見て読んで考える時間が必要である。なのに時間がなさすぎた。もう一度こうした展示がなされるとすれば、その機会を見逃さないようにしたい。
私たちがざっと見るだけのことをし終わるのを待って、青山さんは再び説明してくださった。私たちも次々に疑問が湧いてきて、ついいろいろ質問してしまう。青山さんには感謝しても感謝しきれない。
それにしても、こうした展示を実現し、原型や各種資料を保管管理するムサビの底力にも驚嘆させられた。ムサビの創設者の一人をめぐることとはいえ、なかなかできることではない。
画像:「第2回日彫展(高島屋)」会場風景 1954年
展示は終了しました。
(2019年7月20日、梅雨のあけない東京にて)
かなり不躾で失礼な質問だった。
が、青山さんは、清水多嘉示の実家は長野県でも大きな地主でとくに養蚕で有名な家柄だった、ということを丁寧に教えてくださった。パリへの送金は幾度も行われ、中には当時のお金で80円ほどをパリに送金した記録が残っている、ということさえ教えてくださった。そんなことを伺いながら、私と家人は会場の順路を逆に巡ってしまっていたことに気づくことになった。
清水多嘉示は油絵を学ぶためにパリに行ったのだが、ブールデルの作品と出会って彫刻を始めることになったのだそうだ。だから、パリには油絵用と彫刻用と二つのアトリエがあったそうだ。不覚にも知らなかった。
小ぶりの全身像の前まで連れて行ってくれた青山さんは、これは、初めて作った全身像で、ブールデルから、これはとてもいい作品だからブロンズにしておきなさい、と言われた作品です、と教えてくれたり、戦時中に作られた母子像の前で、こんなギリシャ風の衣服ではなくもんぺ姿にしろ、と言われても決して応じなかった、と聞いています、と教えてくださったり、赤ちゃんが眠っている像の前で、このモデルは私です、と教えてくださったり、素晴らしい首の作品の前で、この作品のモデルはムサビの学生さんだった人で残念ながらもう亡くなられました、と教えてくださったりした。戦後作られた三人の女性が輪になったあの有名なモニュメント作品の原型の前でも、様々なエピソードを教えてくださった。
そんなわけで、お嬢様の解説付きでもう一度、順路通りに鑑賞できたのだった。とても贅沢な時間だった。
それだけではない。青山さんは、出口から一旦出たところの扉の部屋に案内してくださったのである。
そこには、デッサンや油絵、各種資料が部屋中びっしりと、床のたくさんのテーブル上にも、もちろん壁にも梁にも、全く隙間なく、展示されていた。どれも実に興味深く、丁寧に見たり読んだりするには、時間が足りない。会期末に訪れたことを後悔していた。
とりわけ、終戦後すぐの8月16日の日付で、「特攻寺」なるものを提案するためのデッサンが描かれ、文章も書かれていたことに驚いた。こうしたことの意味を考えるにはじっくり見て読んで考える時間が必要である。なのに時間がなさすぎた。もう一度こうした展示がなされるとすれば、その機会を見逃さないようにしたい。
私たちがざっと見るだけのことをし終わるのを待って、青山さんは再び説明してくださった。私たちも次々に疑問が湧いてきて、ついいろいろ質問してしまう。青山さんには感謝しても感謝しきれない。
それにしても、こうした展示を実現し、原型や各種資料を保管管理するムサビの底力にも驚嘆させられた。ムサビの創設者の一人をめぐることとはいえ、なかなかできることではない。
画像:「第2回日彫展(高島屋)」会場風景 1954年
展示は終了しました。
(2019年7月20日、梅雨のあけない東京にて)
土砂降りの国分寺駅に降り立った日のこと
2019-07-19
また梅雨の季節。
6月15日(土)の東京は「土砂降り」の予報が的中していた。ずぶ濡れになる、とためらったが、えいっ! と私と家人は新宿から中央線・特快に乗り込み、国分寺駅に降り立ってバスで武蔵野美術大学を目指した。
あいにくの天気にもかかわらず、ムサビはオープンキャンパスで賑わっていた。その賑わいを“中央”から突破して「清水多嘉示資料Ⅲ」展の会場に向かう。
入り口で傘の雨を払い落とし、鍵のかかる装置(名称が分からない)に傘を預けた。ふと会場の方を見ると、茶色のいわゆる具象彫刻が大小、あたり一面にびっしり犇めいていて、あまりのことにその場で立ち尽くしてしまった。向こうまでずっと広がっている。
気を取り直して一歩二歩と会場入り口へと移動していると、係のお姉さんが、カバンをロッカーに預けてください、と言ってきたので我にかえることができた。
この展示のことは、ある方から教わった。その方は、すごいですよ、と言うのだった。そう聞いて、見たい! という欲望を抑えきれずに、こうしてムサビまでやってきた私と家人なのであったが、想像以上に、すごい! と私は思った。
まず、目の前に広がる作品群のその物量において。
資料によれば、並べられた石膏原型は約240点。壮観である。それらは、ほぼ全て、鋳物工場の煙などで黒に近い茶色で覆われているので、壮観さはさらに増している。
“見張り”のお姉さんの指示に従いカメラだけ携えて、入口から“結界”の向こうに足を踏み入れた。ともかく、目移りがする。一つ一つに目を凝らそうとするのだが、全然うまくいかない。何を見れば良いか分からない。集中できないのである。必死で見ていくが、すごい数である。公募展の彫刻部の展示とか大学の彫刻科の卒展の展示でさえ、もっともっと余裕があるだろう。ともかく、ビッシリ! 文字通り“詰め込まれて”いるのだ。というか、一人の作家がこんなにたくさん作ったのか! と“雑念”が入って、さらに動揺している。おいら、やっぱりサボりすぎたなあ、とすでに負けている。いや最初からとっくに負けているわけだが。
ともかく、一つずつ順番に見ていくしかない。
すごいぞ。
さすが「清水多嘉示」である。今や、とても懐かしい「彫刻」がここにある。
心棒を立てて棕櫚縄を巻きつけ、水粘土をくっつけ、さらにつけたり取ったりしながら手元に形を作り上げていく塑像。絵でいえば、もっともデッサンに近い。“実力”が露わになる。デッサンも塑像も、描いたり消したり=つけたり取ったりしながら、納得いくまで“世界”を追い詰めるのに最適なのだ。そう、清水多嘉示は塑像の彫刻家なのである。
たくさんの全身像を順に見ていくと、やがて「首」の像=「頭像」が少しずつ出てくる。これが素晴らしい。「実力」がいかにも露わなのだ。こんな「首」を作ることができる人は、彫刻家にだってそうそういるわけではない。もう、ごめんなさい! なのだ。
全身像は確かにすごい。すごいが、どれも頭部が異様に小さい、と思う。何故か?
思わず、高村光太郎「雨の日のカテドラル」や「根付の国」のことなどを思い出している。いるが、長続きしない。次々に作品が押し寄せてくるのである。
会場を巡り巡っていると、やがて若き日、パリでブールデルのもとで学んでいた頃に作ったらしき「首」が並んでいるところに行き当たった。
もう、すでに非凡さが露わである。ブールデルに可愛がわれたことが「当然だろう」と頷かれる。
ちょっとデスピオに似た“テイスト”の「首」の作品の前で、いろいろ試していたんだなあ、と家人と話していると、上品なご婦人から話しかけられた。なんと、清水多嘉示のお嬢さん、だった。
(2019年6月19日、6月16日のことを思い出しながら、東京にて)
(ぼやぼやしているうちに、一ヶ月も経ってしまった。すっかり忘れてしまわないうちにもう少し書き留めておきたい。)
つづく→
6月15日(土)の東京は「土砂降り」の予報が的中していた。ずぶ濡れになる、とためらったが、えいっ! と私と家人は新宿から中央線・特快に乗り込み、国分寺駅に降り立ってバスで武蔵野美術大学を目指した。
あいにくの天気にもかかわらず、ムサビはオープンキャンパスで賑わっていた。その賑わいを“中央”から突破して「清水多嘉示資料Ⅲ」展の会場に向かう。
入り口で傘の雨を払い落とし、鍵のかかる装置(名称が分からない)に傘を預けた。ふと会場の方を見ると、茶色のいわゆる具象彫刻が大小、あたり一面にびっしり犇めいていて、あまりのことにその場で立ち尽くしてしまった。向こうまでずっと広がっている。
気を取り直して一歩二歩と会場入り口へと移動していると、係のお姉さんが、カバンをロッカーに預けてください、と言ってきたので我にかえることができた。
この展示のことは、ある方から教わった。その方は、すごいですよ、と言うのだった。そう聞いて、見たい! という欲望を抑えきれずに、こうしてムサビまでやってきた私と家人なのであったが、想像以上に、すごい! と私は思った。
まず、目の前に広がる作品群のその物量において。
資料によれば、並べられた石膏原型は約240点。壮観である。それらは、ほぼ全て、鋳物工場の煙などで黒に近い茶色で覆われているので、壮観さはさらに増している。
“見張り”のお姉さんの指示に従いカメラだけ携えて、入口から“結界”の向こうに足を踏み入れた。ともかく、目移りがする。一つ一つに目を凝らそうとするのだが、全然うまくいかない。何を見れば良いか分からない。集中できないのである。必死で見ていくが、すごい数である。公募展の彫刻部の展示とか大学の彫刻科の卒展の展示でさえ、もっともっと余裕があるだろう。ともかく、ビッシリ! 文字通り“詰め込まれて”いるのだ。というか、一人の作家がこんなにたくさん作ったのか! と“雑念”が入って、さらに動揺している。おいら、やっぱりサボりすぎたなあ、とすでに負けている。いや最初からとっくに負けているわけだが。
ともかく、一つずつ順番に見ていくしかない。
すごいぞ。
さすが「清水多嘉示」である。今や、とても懐かしい「彫刻」がここにある。
心棒を立てて棕櫚縄を巻きつけ、水粘土をくっつけ、さらにつけたり取ったりしながら手元に形を作り上げていく塑像。絵でいえば、もっともデッサンに近い。“実力”が露わになる。デッサンも塑像も、描いたり消したり=つけたり取ったりしながら、納得いくまで“世界”を追い詰めるのに最適なのだ。そう、清水多嘉示は塑像の彫刻家なのである。
たくさんの全身像を順に見ていくと、やがて「首」の像=「頭像」が少しずつ出てくる。これが素晴らしい。「実力」がいかにも露わなのだ。こんな「首」を作ることができる人は、彫刻家にだってそうそういるわけではない。もう、ごめんなさい! なのだ。
全身像は確かにすごい。すごいが、どれも頭部が異様に小さい、と思う。何故か?
思わず、高村光太郎「雨の日のカテドラル」や「根付の国」のことなどを思い出している。いるが、長続きしない。次々に作品が押し寄せてくるのである。
会場を巡り巡っていると、やがて若き日、パリでブールデルのもとで学んでいた頃に作ったらしき「首」が並んでいるところに行き当たった。
もう、すでに非凡さが露わである。ブールデルに可愛がわれたことが「当然だろう」と頷かれる。
ちょっとデスピオに似た“テイスト”の「首」の作品の前で、いろいろ試していたんだなあ、と家人と話していると、上品なご婦人から話しかけられた。なんと、清水多嘉示のお嬢さん、だった。
(2019年6月19日、6月16日のことを思い出しながら、東京にて)
(ぼやぼやしているうちに、一ヶ月も経ってしまった。すっかり忘れてしまわないうちにもう少し書き留めておきたい。)
つづく→




















