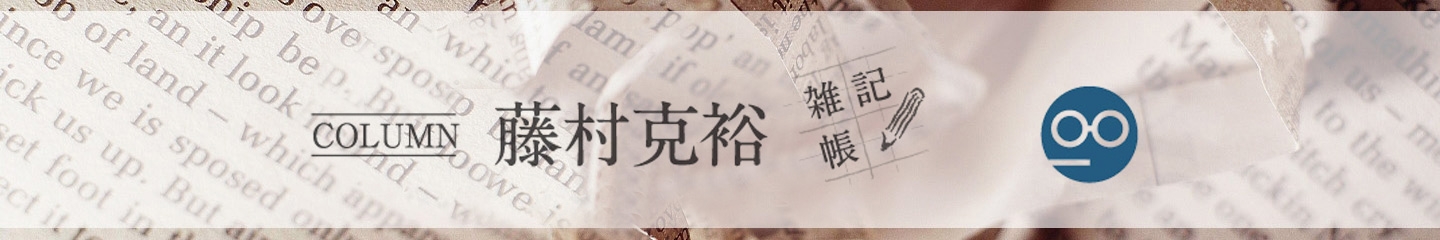
藤村克裕雑記帳283 2025-07-17
「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)

「あかさかみつけ」 1981年作
岡﨑氏のいわば代名詞とも言える通称「あかさかみつけシリーズ」は、1981年3月村松画廊での「たてもののきもち」というタイトルの氏の初個展で発表された。その時の「あかさかみつけ」が、今回は「こづくえ」と同じ部屋の壁に展示されている。
不覚にも私は氏の初個展を見ていない。すでに述べたように、私が岡﨑氏の作品を初めて見たのは1981年11月の「第2回 ハラ・アニュアル」でだった。先輩画家の桜井英嘉氏が、今やってる「ハラ・アニュアル」に出してるから見ておいてよ、と言うので、品川の原美術館へ見に行った。その時に、廊下の壁に展示されていた名前も知らなかった岡﨑氏のいくつかの作品を見たのである。現在言われる「あかさかみつけ」シリーズだった。どの作品だったか、何点あったか、などはもう記憶していない。記憶はないが、とても面白い、と思って、氏の名前を覚えた記憶はある。その時、私はただちにタトリンを思い浮かべていたが、磯崎新氏は「『カタジナ・コブロだね』とニヤリと」言ったそうである(『群像』2025年4月号、田中純氏による岡﨑氏へのインタビュー「シン・イソザキがヨミがえる」での岡﨑氏の発言)。私は1987年にポーランドのウッジを訪れるまでカタジナ・コブロをまったく知らなかったが、岡崎氏は1981年にはすでにもう知っていて磯崎氏と話がはずんだというのだから驚きだ。
今回は、1981年の「たてもののきもち」での発表作のうち、「そとかんだ」「あかさかみつけ」「うぐいすだに」「かっぱばし」の4点が展示されている。「かっぱばし」は個人蔵、それ以外は高松市美術館の所蔵。「うぐいすだに」以外は、先に指摘した“先すぼまり”になっているのが興味深い。この当時の岡﨑氏は空間を包み込みたい、と思っていたということだろうか。その“包み込み”たかったらしき空間と、その外側の空間とが行き来すること。
1981年の「あかさかみつけ」などを見るのは三度目だったが、ジオットの壁画を参考にして着彩したというその色どうしの響きが、鈍く、重苦しく感じさせられて、あまりジオットらしくなく、想定外の印象を受けた。ポリスチレンのボードは建築模型によく使われるようだが、その切断面には空隙がない。そうしたところからの影響があるかもしれない。岡﨑氏は、その切断面にも着彩していて、面への着彩との関係を探っており、複雑な「見え」を実現しようとしている。
観客の視点が変化するたびに(もっと言えば、同一の視点でもそこから視線を動かすたびに)、岡﨑氏のレリーフは次々と表情を変えていく。というか、表情が変化していることに私たちが気付くことをレリーフが促してくる。柔らかな一分節の曲線と直線、面の形状と色の広がり、隙間のかたち、目の位置が動いて隙間が消えた時に手前と奥の面とが一体化する時のヴォリウム感、ネガポジの形状の反復・反転・交錯が生み出す豊かなリズム、、、。これらが豊かで心地よく、見飽きることがない。まさに「こづくえ」からの展開だといえよう。

これらのうち、「あかさかみつけ」については、壁に密着する“部材”への赤と青との着彩の境界が当初は最短部を結ぶように単純に設定されていたことをずいぶん以前に指摘したことがある(拙文「トレースの行方 岡崎乾二郎展」2003年『瓜生通信』。この文については既に触れた)。壁に密着している“部材”の着彩での区分で生じる形状においては、上方の左右のヘリの曲線の形状をそのまま延長して交点を求めて尖った形状を導き出し、その形状で上と下とを物理的に分割して再び接着するように変更して、シャープになった。
また、作品に向かって右側の、観客に向けて立ち上がってくる“部材”では、内側表面を着彩でグレイと水色とで二つに区分し、外側では白とグレイと茶色で同様三つに区分している。ここも、のちには三つに切り分けたのちに再び接着して一つにして“部材”とするように変更している。
こうした細かな変更を、「あかさかみつけ」の向かい側の床に並べて置かれた什器の中に上向きに置かれている「あかさかみつけ」のマケット(1981ー85年)を見ればこれらの変更はこの時点ですでになされており、村松画廊での発表からそう時を置かずにこれらの変更がなされていたのが分かる。この変更は、わずかな違いとはいえ、じつはとても大きな違いで、岡﨑氏のセンスのよさをよく感じさせるものだ。「あかさかみつけ」はより軽快さを増して、クリアになったのである。 この変更とその効果は、ポリプロピレンやポリエチレンで連作した(今回も展示されている)「あかさかみつけ」を見れば、よりはっきりと分かる。

この「あかさかみつけ」シリーズのあと、確か、薄手の段ボール紙などを引き裂いたりして各種の紙を貼り合わせながらつくった作品群があったはずだ(当時、私は北海道にいて実見できていなかったが、一度だけ札幌の道特画廊というところでそうしたレリーフを数点見た記憶がある。氏の年譜を見てみてもその時の発表記録がないので、いつのことだったか確認できない。おそらく、札幌で『美術ノート』を主宰していた佐々木方斎氏が組織したグループ展ではないか、と思うが、これも直ちには確認できない)。また、お茶の水画廊やAndo Galleryでの発表記録があるポリプロピレンによる「亜鉛」などの床置きの大きな作品群も含めて、これらは今回も展示公開されていないのが(SNSでは兵庫県立美術館での「亜鉛」の展示の情報があったが)いかにも惜しい。「3時12分」などの展示で一定の想像はできるが。

ところで、『美術手帖』2025年7月号の特集に登場している山田はじめ氏の「X」を見てみたら、5月14日の投稿に驚かされた。「あかさかみつけ」を展開図にするとベストの前身頃の型紙の「シェイプ」になる、というのである。そのシェイプの「内側に描き足された分割線によって、洋服の柔らかなシェイプが建築を思わせる堅牢な構造へと再解釈されている」。「本作が“厳密な論理に基づいて設計されているようで絶妙に捉えどころのないシェイプ”と感じられるのは、異なる論理に基づいて生み出された内/外のシェイプが立体的にもつれ合い、我々を撹乱しているからに他ならない」と山田氏は書いている。この日の投稿にはその展開図が示されている。また、5月8日の投稿には動画が示されている。すごいぞ。
ほかにも山田氏の「X」への投稿には「そとかんだ」についての投稿、また、「おかちまち」についての投稿も見つけることができる。
すごい人がいるものだ。
また、詩人のカニエ・ナハ氏が『現代詩手帖』2025年7月号に「にゃんだこりゃ」と題した岡﨑展の展評を寄せており、その中で、「うぐいすだに」には「いす」が含まれており、「こづくえ」と対応することを指摘している。さすがだ!

(つづく)
→続き:「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)
https://gazaizukan.jp/fujimura/columns?cid=336
岡﨑乾二郎
而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here
会期:2025年4月29日(火・祝)~7月21日(月・祝)
開館時間:10:00~18:00(展示室入場は閉館の30分前まで)
休館日:月曜日(5月5日、7月21日は開館)、5月7日
会場:東京都現代美術館 企画展示室 1F/3F、ホワイエ
主催:東京都現代美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)
公式HP:
https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/kenjiro/
美術手帖2025年7月号 特集「岡﨑乾二郎」
出版社:美術出版社
発売日:2025年6月6日
公式HP:
https://bijutsu.press/books/5617/
山田はじめ氏
公式X:https://x.com/1yamada
写真1:「あかさかみつけ」
写真2:「あかさかみつけ」部分
写真3:「あかさかみつけ」のマケット
写真4:ポリプロピレンの「あかさかみつけ」
写真5:「3時12分」

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
新着コラム
-
2025-09-01
-
2025-09-01
-
2025-09-01
-
2025-09-01
-
2025-09-01
-
2025-09-01
-
2025-09-01




















