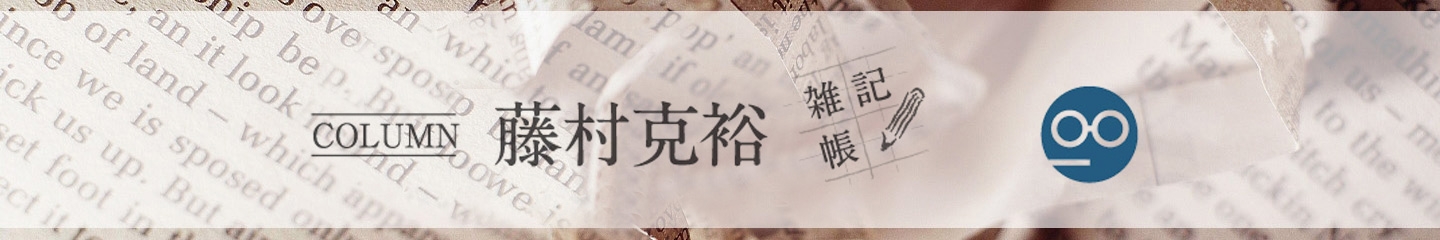

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
燕三条市に行ってきた(3)
2015-12-26
次に「マルナオ」に行った。ここは、見学客でごったがえしていてびっくりさせられた。グループでやって来て見学している人々が多いようだった。この会社では木の箸などを作っている。その様子をガラス越しに見学できる。普段から見学客やワークショップ参加者を受け入れることも想定して作られたモダンな建物。ショップの品揃え。デザイン。地方でもの作りを展開するための工夫が随所に感じられた。
次に訪れた「三条製作所」は、伝統的な手作りのカミソリを作っている工場=こうば。実際の仕事場に入れて下さって、ひとつひとつ本当に丁寧に説明して下さった。裸電球の灯る仕事場は、昔ながらの様子を維持しつつ、今も日々の仕事の現場である事を十分過ぎるくらい示していた。昔は日本刀も作っていたとの事。たたらの鋼と鉄との違いを分かりやすく説明して下さったり、「ふいご」の蓋を開けて中の構造を見せて下さるなど、こうした仕事を絶やさぬためにがんばっておられるご主人の熱意がいたいほど伝わってきた。
その隣にあった「諏訪田製作所」は爪切りで有名な会社。会社入り口のオブジェで、まずギョギョっとさせられ、ギャラリー入り口に掲げられている書の作品にも驚かされた。会社のイメージ作りに力を入れている様子がよく分かる。なので、大変あか抜けている。ガラス越しに職人さんたちの仕事が見学でき、そのコースも実にうまく設定されている。仕事内容を説明するための“中継”映像や文字情報のプレゼンテーションも心憎い。見学者は、完成品を展示しているギャラリーを経て、最後の微調整による仕上げ、研磨…と実際の制作過程の逆の順序をたどって板の形状の素材の段階に至る。それが、効果的だ。ガラスがきれいに磨かれている事はもちろん、採光や照明に至るまで、見学者への気配りが大変細やかだった。道を挟んだショップも無駄なく、しかし贅沢に設定されており、ネール・サロンも設けられているのには舌を巻いた。
次に訪れた「三条製作所」は、伝統的な手作りのカミソリを作っている工場=こうば。実際の仕事場に入れて下さって、ひとつひとつ本当に丁寧に説明して下さった。裸電球の灯る仕事場は、昔ながらの様子を維持しつつ、今も日々の仕事の現場である事を十分過ぎるくらい示していた。昔は日本刀も作っていたとの事。たたらの鋼と鉄との違いを分かりやすく説明して下さったり、「ふいご」の蓋を開けて中の構造を見せて下さるなど、こうした仕事を絶やさぬためにがんばっておられるご主人の熱意がいたいほど伝わってきた。
その隣にあった「諏訪田製作所」は爪切りで有名な会社。会社入り口のオブジェで、まずギョギョっとさせられ、ギャラリー入り口に掲げられている書の作品にも驚かされた。会社のイメージ作りに力を入れている様子がよく分かる。なので、大変あか抜けている。ガラス越しに職人さんたちの仕事が見学でき、そのコースも実にうまく設定されている。仕事内容を説明するための“中継”映像や文字情報のプレゼンテーションも心憎い。見学者は、完成品を展示しているギャラリーを経て、最後の微調整による仕上げ、研磨…と実際の制作過程の逆の順序をたどって板の形状の素材の段階に至る。それが、効果的だ。ガラスがきれいに磨かれている事はもちろん、採光や照明に至るまで、見学者への気配りが大変細やかだった。道を挟んだショップも無駄なく、しかし贅沢に設定されており、ネール・サロンも設けられているのには舌を巻いた。
燕三条市に行ってきた(2)
2015-12-26
次にリサイクルの「北興商事」。じつは、この「工場の祭典」というイベントを見学したい、と思ったのは、この工場で作ったらしい自動車をプレスした直方体の写真がパンフレットにあったから。それが、一時一世を風靡したフランスのセザールの作品みたいでかっこよかったからだ。自動車が直方体になるのを見学できるかもしれない、と思ったのだ。残念ながら、それは危険すぎるそうで見せてもらえなかった。とはいえ、たくさんの使用済みの缶がプレスされて直方体になっていく現場は見学できた。分別されたアルミ缶が音をたてて床下の機械に放り込まれ、大きすぎるくらいのそのプレス機が動き出すのだが、動き出す前に“ピーヒャラピーヒャラ…”とチビまる子ちゃんのテーマが鳴り出す。それが作業員の安全確認の注意を喚起しているとのことである。あの曲だから気分も明るく保持できるのかもしれない。数十秒するとプレスされた直方体が地下の装置から地上へ顔を出す。これが繰り返されるわけである。三方向からのプレス。リサイクル工場、スクラップ工場はなかなか見学させてもらえないという。私もはじめて見学した。この工場の英断はすばらしい。搬入されてさらに丁寧に分別され、こうしてリサイクルのために一定の加工が施されている様子を目の当たりにすると、資源のことを改めて考えさせられる。ギロチンと呼ばれる大きな機械や焼却炉、つみあげられた自動車の車体をはじめ多くのリサイクル素材を目の当たりにして、感動してしまった。見学者のための係のひとの説明も心がこもっていて、現場の使命感や熱意がひしひしと伝わってきた。都市鉱山という言い方がある。しかし、例えば携帯電話に使われるレアメタル。“ガラケー”ではともかく、スマートフォンになってくると、もう少量のレアメタルを取り出すためにコストがかかりすぎてしまってワリにあわない、だから、スマートフォンはリサイクルされない、という話を聞くとじつに複雑な思いがする。パソコンの基盤などでも同様。旧式のものはともかく、現在行き渡っている機種では、金もプラチナも超極薄で取り出しにとてもコストがかかるそうで、いつまで都市鉱山という言葉が生き残るか、もう正直分からない、と説明された。加工技術が進んで、レアメタルの分量が少なくて済むようになった分、同量のレアメタルを取り出すためにはコストがかかりすぎる、というのである。うーん。“新調する方が安い”となれば、だれもリサイクルに手を出さなくなるかも。それは、どうなんだろうなあ…、といろいろ考えさせられた。
燕三条市に行ってきた(1)
2015-12-26
燕三条市に行ってきた。10月1日から4日まで「燕三条 工場の祭典」という大イベントの情報を得たからだ。10月3日、晴天、日帰り。
新潟県の燕三条は金属加工で有名だが、たくさんの工場のうち、68の工場が開放される、というのでは好奇心がむくむくと頭を持ち上げたのだった。とはいえ訪れる事ができたのはごく限られた「こうば」や「こうじょう」だったが、ものすごく面白かった。
まず訪れたのは「火造りのうちやま」。手作りで和釘を中心に、丸かん、掛金、鎹(かすがい)などを製造している。ご主人自らいろいろ説明をして下さり、実際に幾種類かの和釘を作ってみせて下さった。和釘、と言っても用途によって多くの種類があることや、それぞれがじつに合理的に考え抜かれている事を改めて知った。実際に作っているところを拝見すると、いかにも簡単そうに、あっという間に作り上げる。その背後にどれほどの修練があったのか、そしてまた、寒い冬も暑い夏もこの場所でひとり作業に集中していることを思うと頭が下がった。
新潟県の燕三条は金属加工で有名だが、たくさんの工場のうち、68の工場が開放される、というのでは好奇心がむくむくと頭を持ち上げたのだった。とはいえ訪れる事ができたのはごく限られた「こうば」や「こうじょう」だったが、ものすごく面白かった。
まず訪れたのは「火造りのうちやま」。手作りで和釘を中心に、丸かん、掛金、鎹(かすがい)などを製造している。ご主人自らいろいろ説明をして下さり、実際に幾種類かの和釘を作ってみせて下さった。和釘、と言っても用途によって多くの種類があることや、それぞれがじつに合理的に考え抜かれている事を改めて知った。実際に作っているところを拝見すると、いかにも簡単そうに、あっという間に作り上げる。その背後にどれほどの修練があったのか、そしてまた、寒い冬も暑い夏もこの場所でひとり作業に集中していることを思うと頭が下がった。




















