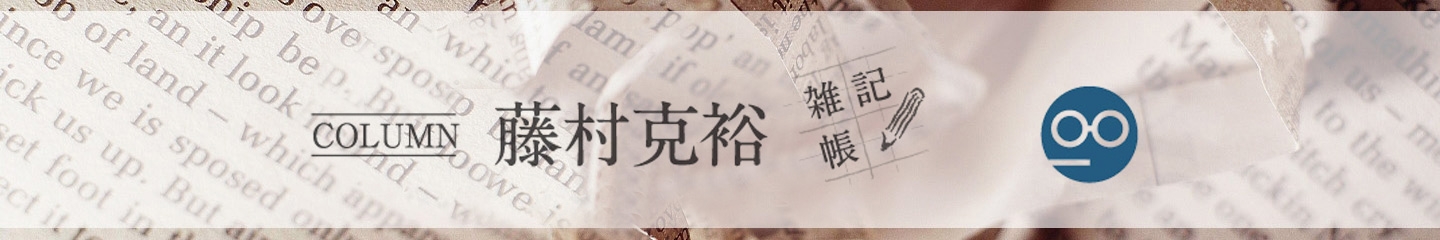

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
友人のムシの居所
2019-05-24
久しぶりに会った古くからの友人が、言うのだった。
このあいだ大阪でボルタンスキーの展覧会を見てきた。出張の限られた時間をやりくりして時間を作ってわざわざ行ったのに、実につまらなかった。あんなことなら、無理せずそのまま新幹線で帰って来ればよかった。
国立国際だっけ? と私。
そう。お前もいつか「画材図鑑」で、近美のゴードン・マッタ=クラーク展の時に書いてたけど、近頃、学芸員が余計なことをしすぎるんじゃないか? 雰囲気作りが過剰っていうか、作品の読み取り方を誘導しすぎる、っていうか。
そんなにひどかった?
ああ、そう思った。越後妻有のボルタンスキーはとてもよかったのに。
わかりやすそうなウケ狙いの展示のやり方を大学の学芸員課程とかで教えてるのかもなあ。だから、近美の高松(次郎)さんの時やマッタ=クラークの時みたいに押し付けがましくなるのかも。
お前にも責任があるぞ。
なんで?
大学で教えてただろ。
俺のいた部署では展示のことは教えてなかったよ。
いや、絶対に責任がある。
ないよ。
ごまかすなよ。
もう少しやり取りは続いたが、友人はムシの居所が悪かったのだろう。
このあいだ大阪でボルタンスキーの展覧会を見てきた。出張の限られた時間をやりくりして時間を作ってわざわざ行ったのに、実につまらなかった。あんなことなら、無理せずそのまま新幹線で帰って来ればよかった。
国立国際だっけ? と私。
そう。お前もいつか「画材図鑑」で、近美のゴードン・マッタ=クラーク展の時に書いてたけど、近頃、学芸員が余計なことをしすぎるんじゃないか? 雰囲気作りが過剰っていうか、作品の読み取り方を誘導しすぎる、っていうか。
そんなにひどかった?
ああ、そう思った。越後妻有のボルタンスキーはとてもよかったのに。
わかりやすそうなウケ狙いの展示のやり方を大学の学芸員課程とかで教えてるのかもなあ。だから、近美の高松(次郎)さんの時やマッタ=クラークの時みたいに押し付けがましくなるのかも。
お前にも責任があるぞ。
なんで?
大学で教えてただろ。
俺のいた部署では展示のことは教えてなかったよ。
いや、絶対に責任がある。
ないよ。
ごまかすなよ。
もう少しやり取りは続いたが、友人はムシの居所が悪かったのだろう。
「このどうしようもない世界を笑いとばせ 福沢一郎展」 その2
2019-05-17
太い筆で乗せたほぼ一分節の筆触の重なりや連なり。これが画面に作り出している心地よいリズム。手際も良すぎるくらいで無駄がほとんどない。ちょっと驚かされる。この“画風”が検挙されるまで安定的に続く(検挙後も時々顔を覗かせるが、深入りしない)。
それが一変するのは検挙後に描かれた海の絵。絵の作り方を根本的に変化させている。そうでもしなければ“擬態”できなかったのかも。油絵のオーソドックスな技法=重層の技法で描かれた海の絵は、最上層のビリジアンの透層の効果を最大限に引き出している。大変な力量である。これら海の絵は、一種の「戦争画」と言えるのだろうが、「戦争」を真正面から描くことを避けて“擬態”している。福沢一郎は、こういう対応ができる人だったわけだ。というか、こういう対応でもしなければ、描き続けられなかった=生き続けられなかったのかもしれない。
戦後の絵も、え? こんなに良かったか? というくらい見応えがあった。1930年代のピカソの絵からの影響がそこかしこに見出せる時期もあるが、その時期でさえこなれている。というか、巧みに自分のスタイルにしている。驚くほど器用だ。
アクリル絵の具を使うようになって、色彩に鮮やかさが増す。ダンテ『神曲』や源信『往生要集』などを手掛かりに描いているが、ある種、使命感のようなものを抱き続けていた人のように見えた。
もう一度じっくり見たいが、会期終了間近。果たせるかどうか。
(2019年5月17日 東京)
それが一変するのは検挙後に描かれた海の絵。絵の作り方を根本的に変化させている。そうでもしなければ“擬態”できなかったのかも。油絵のオーソドックスな技法=重層の技法で描かれた海の絵は、最上層のビリジアンの透層の効果を最大限に引き出している。大変な力量である。これら海の絵は、一種の「戦争画」と言えるのだろうが、「戦争」を真正面から描くことを避けて“擬態”している。福沢一郎は、こういう対応ができる人だったわけだ。というか、こういう対応でもしなければ、描き続けられなかった=生き続けられなかったのかもしれない。
戦後の絵も、え? こんなに良かったか? というくらい見応えがあった。1930年代のピカソの絵からの影響がそこかしこに見出せる時期もあるが、その時期でさえこなれている。というか、巧みに自分のスタイルにしている。驚くほど器用だ。
アクリル絵の具を使うようになって、色彩に鮮やかさが増す。ダンテ『神曲』や源信『往生要集』などを手掛かりに描いているが、ある種、使命感のようなものを抱き続けていた人のように見えた。
もう一度じっくり見たいが、会期終了間近。果たせるかどうか。
(2019年5月17日 東京)
「このどうしようもない世界を笑いとばせ 福沢一郎展」 その1
2019-05-17
東京・竹橋の国立近代美術館で福沢一郎の作品群をまとめて見た。
正直、ほとんど期待していなかったが、これが面白かった。
入場後、最初に目に飛び込んできた正面の絵が、即座に前田寛治を連想させた。まず、色彩において。同時におおらかな形状把握において。
とてもいい。
近頃、こういう絵にはほとんどお目にかかれなくなった。もちろん、自分でも到底描けそうにない。
色彩は、明るいベージュからほぼ黒までの茶系の一群に独特な緑(オリーブ色?)が関係して、これは言ってみれば補色どうしなんだけど、その取り合わせがとってもきれいで、お、これはあなどれない、といきなり“用心”させられたくらい。
そして驚かされたのは、形状把握だ。細部にこだわらず、しかし細部のニュアンスをしっかり含んで、たっぷりとおおらかである。このたっぷりさがとても懐かしい。マッスという今や死語に近い造形言語が、ここには確かに息づいている。マッス、と言えば、「塊(かたまり)」の感じのことだけど、福沢の場合、必要以上にゴロンとした重苦しいマッスではなく、伸びやかで気持ちがいい。なので、エルンストに似た、とか言われる最初期の絵柄(確かにそうなのだが)がどうであれ、描かれているものの意味やものどうしの関係の意味や無意味、シュルレアリスムのことなどをほとんど考える必要もなく、ただ楽しんでいる自分を見出していたのである。
つづく→
正直、ほとんど期待していなかったが、これが面白かった。
入場後、最初に目に飛び込んできた正面の絵が、即座に前田寛治を連想させた。まず、色彩において。同時におおらかな形状把握において。
とてもいい。
近頃、こういう絵にはほとんどお目にかかれなくなった。もちろん、自分でも到底描けそうにない。
色彩は、明るいベージュからほぼ黒までの茶系の一群に独特な緑(オリーブ色?)が関係して、これは言ってみれば補色どうしなんだけど、その取り合わせがとってもきれいで、お、これはあなどれない、といきなり“用心”させられたくらい。
そして驚かされたのは、形状把握だ。細部にこだわらず、しかし細部のニュアンスをしっかり含んで、たっぷりとおおらかである。このたっぷりさがとても懐かしい。マッスという今や死語に近い造形言語が、ここには確かに息づいている。マッス、と言えば、「塊(かたまり)」の感じのことだけど、福沢の場合、必要以上にゴロンとした重苦しいマッスではなく、伸びやかで気持ちがいい。なので、エルンストに似た、とか言われる最初期の絵柄(確かにそうなのだが)がどうであれ、描かれているものの意味やものどうしの関係の意味や無意味、シュルレアリスムのことなどをほとんど考える必要もなく、ただ楽しんでいる自分を見出していたのである。
つづく→




















