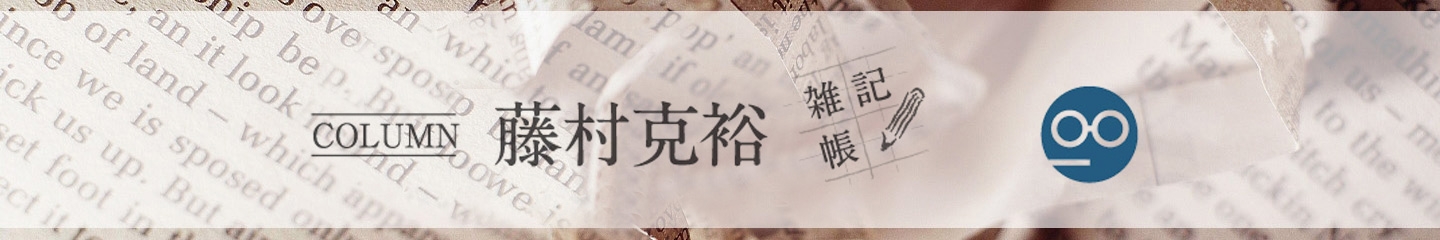

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。
藤村克裕 プロフィール
1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。
1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。
元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。
笠間、茨城県陶芸美術館「井上雅之展」
2022-08-29
「井上雅之展」の会期終了が目前であった。井上氏とは古くからの知り合いである。この大きな展示は見逃せない。8月25日朝、笠間を目指して電車に乗った。
昔々、私は、「どばた」と呼ばれる目白の美術予備校で、3年半の間、非常勤の講師をしていたことがあった。
なぜ、「3年半の間」と「半」がつく半端な期間だったのか? それは9月からの中途採用だったからである。
前任者の“新人”が一学期だけで辞めてしまったとかで、急遽私が雇われたのだった。私だってれっきとした“新人”だったが、コース主任の数野繁夫さんは、その前任者が担当していたクラスをそっくりそのまま私が引き継ぐように、と言った。そのクラスの学生たちの中に井上氏がいたのである。だから、氏と知り合ってから40年以上になる。
クラスの二十数名の一人一人が実に個性的だった。誰もが美大で勉強したいのに合格できなくて、“予備校”と呼ばれる場に高額の授業料を払って身を置いている。なのに、夏休みが終わったらクラス担当が急に代わっていて、見ず知らずの私が急に現れたのだから、彼らには迷惑なことだっただろう。
私にしても、勝手がわからず、無手勝流たらざるをえなかった。実に濃密な時間を過ごさせてもらった。
幸い、じきに彼らは私を受け入れてくれて、本当にいい奴らだった。今だったら、もっときちんと彼ら一人一人の役に立てたのではないか、と考えることもあって、忸怩たるものがある。が、もう絶対に引き返せない。
出会ってから半年後、井上氏は多摩美術大学に入学していったが、入学までの“春休み”にお母さんと一緒に「どばた」に挨拶に来て、それも記憶に残っている。
タマビでは油絵のコースに陶芸のコースが併設されているので、今はあまり絵を描かずに陶芸をやってます、と当人から聞いたことがあった。私が発表活動を始めた頃だっただろうか。油絵コースになぜ陶芸コースが併設されているのか分からないながら、へえ、そうなんだ、と思ったのを覚えている。
その何年か後、やはりその「半年間」、私のクラスにいて井上氏と同じ春に愛知芸大に行った丹下敬文氏から、井上が頑張ってるらしいよ、と聞いたこともあった。
丹下氏は卒業後、東京で仕事していた時期もあったが、やがて名古屋に“戻って”今も名古屋に住んでいる。名古屋の丹下氏から東京の井上氏の近況を聞かされたワケだ。ともかく、その頃には井上氏は着実に頭角をあらわしていたのだろう。
氏の作品をジカに見たのは、それからさらに時間を経てからだった。確か、「現代陶芸」というか、「クレイワーク」という括りで構成した企画展でだった。どこかデパートのようなところを会場にしていたような曖昧な記憶である。その展覧会には、真鍮で大きな螺旋状のパイプを作ってそれに一抱えの素焼きらしき“球”をいくつも取り付けたような作品もあったから、随分柔軟な枠組みの展覧会だったのではないだろうか。何かの宣伝媒体に井上氏の名前を見つけて出かけて行ったはずだ。
その時には、すでに彼のスタイル(別の複数の作品の断片、というか破片、を集めて、構成していくスタイル)は出来上がっていて、神戸生まれ神戸育ちの氏の垢抜けた色や形のセンス、その良さが十分に見てとれて、なんだか嬉しくなって手紙を書いて送った記憶がある。
その後もたびたび彼の作品には触れてきたが、まとめて見るのは今回が初めてだ。
最初期の1982年の作品から今年2022年の作品まで、出品リストによれば70点近く。マケットやドローイング、リトグラフもあったが、大きな作品が多かった。
昔々、私は、「どばた」と呼ばれる目白の美術予備校で、3年半の間、非常勤の講師をしていたことがあった。
なぜ、「3年半の間」と「半」がつく半端な期間だったのか? それは9月からの中途採用だったからである。
前任者の“新人”が一学期だけで辞めてしまったとかで、急遽私が雇われたのだった。私だってれっきとした“新人”だったが、コース主任の数野繁夫さんは、その前任者が担当していたクラスをそっくりそのまま私が引き継ぐように、と言った。そのクラスの学生たちの中に井上氏がいたのである。だから、氏と知り合ってから40年以上になる。
クラスの二十数名の一人一人が実に個性的だった。誰もが美大で勉強したいのに合格できなくて、“予備校”と呼ばれる場に高額の授業料を払って身を置いている。なのに、夏休みが終わったらクラス担当が急に代わっていて、見ず知らずの私が急に現れたのだから、彼らには迷惑なことだっただろう。
私にしても、勝手がわからず、無手勝流たらざるをえなかった。実に濃密な時間を過ごさせてもらった。
幸い、じきに彼らは私を受け入れてくれて、本当にいい奴らだった。今だったら、もっときちんと彼ら一人一人の役に立てたのではないか、と考えることもあって、忸怩たるものがある。が、もう絶対に引き返せない。
出会ってから半年後、井上氏は多摩美術大学に入学していったが、入学までの“春休み”にお母さんと一緒に「どばた」に挨拶に来て、それも記憶に残っている。
タマビでは油絵のコースに陶芸のコースが併設されているので、今はあまり絵を描かずに陶芸をやってます、と当人から聞いたことがあった。私が発表活動を始めた頃だっただろうか。油絵コースになぜ陶芸コースが併設されているのか分からないながら、へえ、そうなんだ、と思ったのを覚えている。
その何年か後、やはりその「半年間」、私のクラスにいて井上氏と同じ春に愛知芸大に行った丹下敬文氏から、井上が頑張ってるらしいよ、と聞いたこともあった。
丹下氏は卒業後、東京で仕事していた時期もあったが、やがて名古屋に“戻って”今も名古屋に住んでいる。名古屋の丹下氏から東京の井上氏の近況を聞かされたワケだ。ともかく、その頃には井上氏は着実に頭角をあらわしていたのだろう。
氏の作品をジカに見たのは、それからさらに時間を経てからだった。確か、「現代陶芸」というか、「クレイワーク」という括りで構成した企画展でだった。どこかデパートのようなところを会場にしていたような曖昧な記憶である。その展覧会には、真鍮で大きな螺旋状のパイプを作ってそれに一抱えの素焼きらしき“球”をいくつも取り付けたような作品もあったから、随分柔軟な枠組みの展覧会だったのではないだろうか。何かの宣伝媒体に井上氏の名前を見つけて出かけて行ったはずだ。
その時には、すでに彼のスタイル(別の複数の作品の断片、というか破片、を集めて、構成していくスタイル)は出来上がっていて、神戸生まれ神戸育ちの氏の垢抜けた色や形のセンス、その良さが十分に見てとれて、なんだか嬉しくなって手紙を書いて送った記憶がある。
その後もたびたび彼の作品には触れてきたが、まとめて見るのは今回が初めてだ。
最初期の1982年の作品から今年2022年の作品まで、出品リストによれば70点近く。マケットやドローイング、リトグラフもあったが、大きな作品が多かった。
上野・国立西洋美術館に行ってきた
2022-08-22
夏だから暑いのは当たり前だが、最高気温が35℃くらいでもあまりびっくりしなくなっている自分が怖い。とはいえ暑すぎて、つい動きがカンマンになっている。それでも、午後からの豪雨に注意、とテレビの気象予報士が言っている日の、その午後に、傘を持って上野・西洋美術館に行ってきた。「国立西洋美術館リニューアルオープン記念『自然と人のダイアローグ』フリードリッヒ、モネ、ゴッホからリヒターまで」展。
ドイツにエッセンという街があって、そこにフォルクヴァング美術館という美術館があるのだそうである。なんでもその美術館はカール・エルンスト・オストハウスという人のコレクションをもとに設立されたらしく、松方幸次郎のコレクションをもとに設立された国立西洋美術館との間にはそういう共通点があるらしい。加えて、オストハウスさんと松方さんとはほぼ同世代だった、ということもあっての企画、ということであった。フォルクヴァンク美術館のコレクションから約40点、残りを国立西洋美術館のコレクションから選んで、総数約100点で構成している。ふだん見慣れた国立西洋美術館のコレクション作品も他の美術館所蔵の見慣れぬ作品を横に置けば、その見え方や解釈が変わるのではないか、ということのようである(私の考えでは、そんなことでは変わりっこない、と思われる)。改修工事終了を記念しての展覧会でもある。改修で、特に美術館前の広場がガラリと変化した。
ところが、私は解説文もキャプションも全く読まずに、へえー、とか、ふーん、とか言いながら、ざっと“流して”見てしまった。2000円の入場料のモトを取ろうとするような見方ではなかったのである。それには途中から気がついていた。が、そのままであった。如何ともし難かった。“暑さ疲れ”というやつであろうか。
それにしても展覧会の入場料が高くなった。ビンボー人がおいそれと出かけられる値段ではない。なんとかしてほしい。
“流して”しまったとはいえ、足を止めて、遠近両用メガネを全面老眼鏡に掛け替えて見入った作品がなかったわけではない。ロドルフ・ブレダンの版画作品は出品作全部が国立西洋美術館の所蔵だが、じっくり見入ってしまった。国立西洋美術館所蔵の作品だと、ちょっとソンをした気分になるのが私の貧乏性を露わにしている。純粋な気持ちで作品を見たいものだが、ソンとかトクとか、そういう雑念が邪魔をしてくるのである。
ブレダンの作品の前でなぜメガネを掛け替えたくなったか?
老眼の度が進んで、昔作った遠近両用では近くが見えにくくなった、ということもあるが、遠近両用だとピントの合う視野が狭いので、ロボコップのように頭を動かして視線を変えていく必要がある。それが煩わしい。全面老眼鏡だと頭を動かさずに目玉だけを動かせば画面のどこでも詳しく見ることができる。どこまでも細部に分け入っていけるし、分け入った先から別のところへ、と視線のジャンプがたやすい。ブレダンの作品はそういうことを促してくる。いつ出会っても、いいなあ、と素直に思う。今回も堪能ということをした。
ドイツにエッセンという街があって、そこにフォルクヴァング美術館という美術館があるのだそうである。なんでもその美術館はカール・エルンスト・オストハウスという人のコレクションをもとに設立されたらしく、松方幸次郎のコレクションをもとに設立された国立西洋美術館との間にはそういう共通点があるらしい。加えて、オストハウスさんと松方さんとはほぼ同世代だった、ということもあっての企画、ということであった。フォルクヴァンク美術館のコレクションから約40点、残りを国立西洋美術館のコレクションから選んで、総数約100点で構成している。ふだん見慣れた国立西洋美術館のコレクション作品も他の美術館所蔵の見慣れぬ作品を横に置けば、その見え方や解釈が変わるのではないか、ということのようである(私の考えでは、そんなことでは変わりっこない、と思われる)。改修工事終了を記念しての展覧会でもある。改修で、特に美術館前の広場がガラリと変化した。
ところが、私は解説文もキャプションも全く読まずに、へえー、とか、ふーん、とか言いながら、ざっと“流して”見てしまった。2000円の入場料のモトを取ろうとするような見方ではなかったのである。それには途中から気がついていた。が、そのままであった。如何ともし難かった。“暑さ疲れ”というやつであろうか。
それにしても展覧会の入場料が高くなった。ビンボー人がおいそれと出かけられる値段ではない。なんとかしてほしい。
“流して”しまったとはいえ、足を止めて、遠近両用メガネを全面老眼鏡に掛け替えて見入った作品がなかったわけではない。ロドルフ・ブレダンの版画作品は出品作全部が国立西洋美術館の所蔵だが、じっくり見入ってしまった。国立西洋美術館所蔵の作品だと、ちょっとソンをした気分になるのが私の貧乏性を露わにしている。純粋な気持ちで作品を見たいものだが、ソンとかトクとか、そういう雑念が邪魔をしてくるのである。
ブレダンの作品の前でなぜメガネを掛け替えたくなったか?
老眼の度が進んで、昔作った遠近両用では近くが見えにくくなった、ということもあるが、遠近両用だとピントの合う視野が狭いので、ロボコップのように頭を動かして視線を変えていく必要がある。それが煩わしい。全面老眼鏡だと頭を動かさずに目玉だけを動かせば画面のどこでも詳しく見ることができる。どこまでも細部に分け入っていけるし、分け入った先から別のところへ、と視線のジャンプがたやすい。ブレダンの作品はそういうことを促してくる。いつ出会っても、いいなあ、と素直に思う。今回も堪能ということをした。




















